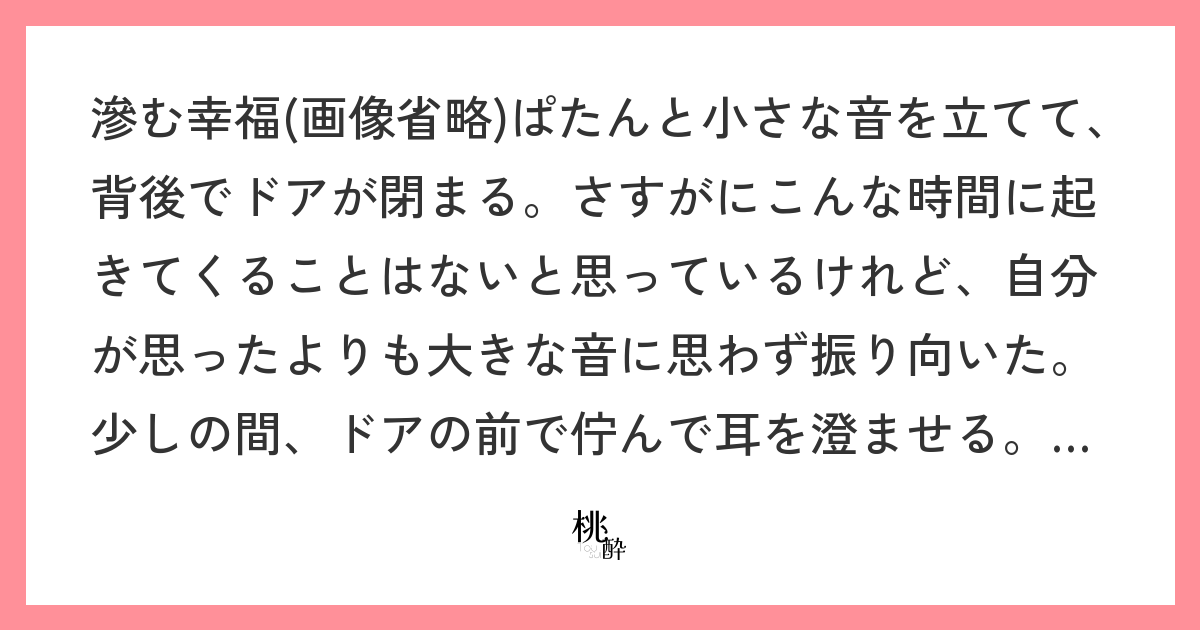2022年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
甘言蜜語
2022/05/06
「ねーぇ、トーちゃん♡ この間のジョークグッズのクッキーって、どこで買えるの?」
事務所で友人――事務所ナンバーワンの男優、チヒロに突然そう声を掛けられて俺は思わず「あ?」と胡乱な返事をした。
……いや、この場合俺は悪くないだろ。つい先日、俺が差し入れた|ジョークグッズ《若返りクッキー》のせいで事務所はその翌日、それはそれは大変な目に遭ったところだ。俺はもちろん、チヒロも含めて事務所の中でも売れっ子組がこぞって肉体が若返って、リスケが死ぬほど大変だったのだと俺はこっぴどく事務所統括マネージャーの岡持に怒られた。当面事務所のスケジューリングに文句を言わない、という譲歩をしてようやく《《渋々ながら》》岡持の溜飲が下がった程度である。ついでに数日間いいメシを奢らされた。さすが統括マネージャーだけあって、岡持はああみえてちゃっかりしている。
そんなわけで、俺は今日も罪滅ぼしもかねて、撮影の合間に事務所の手伝いをしていた――のだが。
「……なんでだよ」
俺はもう社長と岡持に挟まれて怒られんのは勘弁だぞ、と顔をしかめてそう言えば、チヒロは「あはは」と軽く笑い飛ばした。……今の俺からしたら笑い事じゃねえっつーの。
「ちがうちがう、この間は俺しか食べなかったからさ♡ 小さい久遠ちゃんも見てみたいなーって……♡」
「……本人の同意は」
間髪入れずにそう尋ねると、チヒロは茶目っ気たっぷりにウインクをして見せてから「これから♡」と返事を寄越す。なにが〝これから〟だと悪態をついてから、あのなぁと頭を掻いた。チヒロは自分が男女問わず人たらす能力があるのをいいことに、こうしてときおりノリと勢いで押し切ろうとする節がある。さすがに付き合いの長い俺や岡持、社長をはじめとした面々には効かないのだが……。ある程度のことであれば、《《これ》》で許されてきたせいでこのあたりコイツは緩い。
「よーし、チヒロ。おまえはまず本人の同意を得ろ。じゃないと死んでも俺はクチを割らねえぞ」
「……ふーん、そっか。じゃあこのトーちゃんが探してたヤツ、残念だけど別の人に譲ろうかなー」
この反応も予想していたのか、チヒロはガサガサと手にしていた紙袋からモノを覗かせて、これ見よがしに揺さぶりをかけてくる。しかも、探していたモノとはいわゆる絶版モノだ。趣味は正反対と言ってもいいチヒロには不要の長物だが、俺からすれば垂涎ものの品である。
「おまえ……そういうのはズルだろ!」
そう叫んで、あの子には申し訳ないなと思いつつ……俺はチヒロの持ち掛けた取引に応じることにしたのだった。
◇ ◆ ◇
もぞり、と身動ぎをすると枕元に置いてあるスマフォへと手を伸ばす。ぱた、ぱた、と手探りで探り当てて手に取ると、まだ重い瞼を開けた。
「んん……まだ八時前かぁ……」
それなりには寝たのだが、朝の気怠さはどうしたって軽減しないなぁと思う。美容の大敵だからと普段は早寝を心掛けているとはいえ、不規則な仕事のスケジュール柄、夜遅くなることも少なくはない。あれやこれやと今日やることを頭の中で考えつつ、隣ですやすやと穏やかな寝息を立てている彼女に目を向けた。
少しだけ丸まるようにして眠る姿を見るたびに、やっぱり小動物みたいだなぁと思う。ちょこちょこと動くところも相まって、起きているときにはどちらかと言えば活発に思える姿も、寝ているときは本当にちいさくて可愛らしい。
起こさないようにゆっくりと体勢を整えると、身体を包むようにやさしくぎゅうと抱きしめた。鎖骨の下――ちょうどタトゥーの辺りに彼女のあたたかい呼気が当たって、くすぐったい。そっと視線を下ろすと、まだ眠っている久遠ちゃんが、鼻先をすり寄せるようにしてちいさく動いたところだった。動きに合わせて、さらさらと細くて滑らかな髪が揺れる。俺の匂いに安心しているのかなぁと思うと、またたまらなく愛しさがこみ上げてきてしまう。……彼女と暮らすようになってからは毎日そう思ってばかりだし、これからもずっと飽きることはないだろうと、自信を持って言えるほどだ。
「んー、ふふ……っ」
彼女は先に寝てしまうことが多いから知らないけれど、《《まだ足りないな》》と思った日にこの寝顔をオカズにしている俺としては、休日は朝からそういう日にしたっていいんだけど。それとは別に彼女との普通の生活も楽しみたいという気持ちもあるので、どうしたものかなぁと寝顔を眺めながら思考を巡らせる。
考えながら、薄く開いたままになっている久遠ちゃんの薄い唇を指の腹で突いて、閉ざすように指を動かした。頭がぼんやりしてきたときや、こうして眠っているとき、彼女は口元が若干疎かになる。そういう無防備なところもかわいいんだけど、よそでもこうなのかなぁと思うと少しばかり心配な気持ちにもなる。
脱線した思考のせいで複雑な気持ちになって、俺はつつ……と指の腹でその唇を撫でた。
「んん……」
ほとんど吐息のような声を上げて、眉が寄せられる。ゆるやかに|頭《かぶり》を振ると、またすうすうと寝息を立て始めた彼女の様子を見て、そっと声を上げずに笑う。ふと湧いた悪戯心に、寝ている彼女の唇を、つんつんと軽く突く。反射的に開いた唇の隙間から、わずかに覗いた歯列をなぞると、先ほどと同じように薄く開けられた。安心しきっているとはいえ、これを眠ったままやっているのだから……余計に心配にもなってくる。悪戯を仕掛けたときには、そこまでするつもりはなかったのだけど、逡巡の末に赤い舌の上に指先を触れさせれば、舌先が形を確かめるようにしてなぞっていく。
ぬるりと温かな舌先が爪先を擽ってからしばらく。ん、と先ほどよりも大きく、無防備に晒された舌に、誘われるようにして指を乗せた。ゆるゆると舌先が上へ下へと指を舐めては、控えめに指に吸いつかれる。唾液の絡んだ指を上顎へ這わせると、「んぅ」とくぐもった声が鼻先から零れた。音とともに追いかけてきた舌が、次は指の腹側ではなく甲の側を這っていく。切なげに寄せられた眉と言い、若干上気して染まった頬と吐息と言い。目覚めてはいないからその目が俺の方を向いていないと言うだけで、その表情は俺がよく知る情事中の彼女の表情だ。……それも、《《欲しがっているとき》》のそれ。
「はー……もう」
俺がそうしたのは紛れもなく事実なんだけど。眠っていて安堵しきった状態で、反射的にこんなことをされちゃったら、組み立て始めた予定とか、もうどうでもいいかなー……と言う気持ちになってくる。ずるりと指を引き抜くと、彼女の口腔内から引いた糸を拭って、俺はそっとベッドから抜け出す。
「さすがに久遠ちゃんが悪いよねぇ、これは」
自室に置いた荷物の中からお目当てのものを持ってくると、彼女が目覚めるまでもうしばらくの間……その寝顔を眺めていることにした。
◇ ◆ ◇
「んん……ん」
ちいさな声とともにもぞもぞと身体を起こす布擦れの音が聞こえて、俺は家事を中断して彼女のもとに歩み寄った。まだ意識が覚醒しきっていないのか、目元を擦りながらその上体はふらふらとちいさく揺れている。
「久遠ちゃん、おはよ♡」
「……おはよう、ございます……ちひろさん」
寝起きの彼女の声はいつも以上にぽわぽわとしていて、呂律もたどたどしい。ふふっとちいさく笑って、先だって持ち出して来ていた《《お目当ての品》》の封を開ける。一枚指で摘むと、彼女の口元へと運ぶ。
「ほーら、久遠ちゃんお口開けて?」
「んー……ん、はぁーい……」
疑問に思うことなく「あーん」と口を開けた彼女の口に、クッキーを咥えさせる。指でそれを支えるようにして待てば、若干戸惑いつつも久遠ちゃんは大人しくもぐもぐと咀嚼をし出す。そのクッキーは、先日若返りを起こした例のジョークグッズだ。あのとき、誰も何も疑問に思わなかったほど、味としては〝普通の美味しいクッキー〟である。案の定、彼女も疑問に思わなかったのか、ちみちみと食べ進んでいく。彼女の口の動きに合わせて、最後のひと欠片を指で押し込むようにして、口に入れた。そのままの流れで、ふに、と軽く唇へ触れる。
「んむ……?千弘さん、なんで朝からクッキーを……?」
嚥下してからそう首を傾げた彼女に、俺は「前に食べておいしかったから、久遠ちゃんにもお裾分け♡」と笑ってみせた。戸惑い気味に「なるほど……?」と首を傾げた彼女の思考を遮るようにして、指をそのまま口に入れる。
「んっ……、ちひろさん……?」
なんでと問いかけてくる視線に、ふわりと笑って「指にも欠片ついちゃってた♡ 久遠ちゃんなら、どうすればいいかわかるよね?」と返事を返した。さっと朱のさした頬の色に、喉奥でくつくつとちいさく笑う。本当に、快感に対して素直でかわいい子だなぁと思うと、余計に愛しさが溢れてくる。どれもこれも俺が教えて、俺相手だから覚えてくれたことなんだと知っているからこそ、余計にそう思うのだ。
「うぅ……」
恥ずかしそうにしながらも、指先に舌が触れる。意識してしまっているのか、触れたソレは明らかに熱を持っていた。ぺろり、と指先を舐め上げられる。
「ふふっ、素直に言うこと聞けていい子……♡」
そう言いながら空いた片手でする、と喉をひと撫ですると、ひくりとちいさく喉が震えた。口内もすっかり弱くなった彼女は、今では口の中まで性感帯になっている。ゆるゆると俺の指を舐めているだけで、彼女の目が徐々にとろんと堕ちていく。最初は躊躇いがちだった舌の動きが、もっとほしいと強請るような動きに変わった。必死に指の股まで舐めている彼女の鼻先から、甘い声が抜けていく。寝起きでこんなことを急に強要されたと言うのに、一方で俺にとことん愛し尽くされた身体は、素直にこの先の快感を期待しているのが見て取れた。浅くなっていく呼吸が、息継ぎの合間から洩れるペースがどんどん上がっていっている。
「ち、ひろさ……」
咥内に溜まった唾液をこぼれないように必死に嚥下しながら、震える声で名を紡がれる。その声が甘えたような響きを帯びていることに、俺が気付かないわけもなく。そうと悟られないようにくすりと笑ってから、口に含まれたままになっていた指をぬるり、と引き抜いた。ほんのすこし残念そうな表情を覗かせて、俺の指を追いかけるようにして、ちいさくくぐもった声が漏れる。反応するように喉が震えるところが、また可愛らしい。
――ここまで来れば、もう久遠ちゃんは断らない。否、断れない。彼女自身うっすらと気付いているだろうけれど、俺が〝気持ちいいのを隠さないで〟と言い続けてきたのはそういう理由だ。隠さずに晒け出せば晒け出すだけ、身体はより素直に快感を追おうとする。それを何度も何度も。……繰り返し、彼女と彼女の肉体に教え込んだのは、ほかの誰でもない。|高嶺千弘《俺》なのだから。プロとして得たテクニックも、彼女を愛するひとりの男としてのして情念も。数ヶ月以上にわたってぶつけて、すっかり蕩けさせてきた。今では素直な彼女は、俺が顔を寄せたり身体を抱き上げただけで真っ赤になってしまうくらい、意識づけられている。
「ね、キスしよっか……♡ お口あけて?」
唾液ですっかりふやけた指先を舐めとると、彼女の髪を耳に掛けた。指先が敏感な耳に触れて、ちいさく身体が震える。ぴくっと小刻みに震えたのを視認して彼女の顔を見ると、気恥ずかしさからかふいと視線を逸らされてしまった。あらら……と笑って視線を追いかける。追いかけた先で目元まで赤くした久遠ちゃんが、俺が視線を向けたのを見てちいさく口を開けた。その様子に、思わず「ふふっ」と笑みがこぼれ落ちる。照れてはいても素直に言うことは聞いちゃうんだもんなぁ、とそんなところがいじらしくてより愛しさが溢れてくる。
「……いい子♡」
そう言って頬に手を添えて、唇を合わせた。滑り込ませた舌先で歯列をなぞると、くぐもった声が口腔内で響いた。逸らしたはずの視線が、いつの間にか俺の方へ戻されているのを見て本当に素直だなぁと嬉しくなる。これが、俺相手だからこそなんだと思うと……どこまでも底抜けに幸福感で支配されそうになってしまうほど。控えめに伸ばされて絡められた、薄い舌を絡めとるようにしてより深く。もっと深く……と、貪るようにしてそれを繰り返した。
◇ ◆ ◇
「ふぁぁ……んー、よく寝た……♡」
小声でそう言いながら、ぐぐっと伸びをする。結局朝から《《そういう気分》》になってしまったので、そのままの流れでいつものように抱いたのだった。早めに起きたこともあって、ふわふわと眠気に纏わりつかれてうつらうつらしている久遠ちゃんを寝かせて、俺ももうひと眠りすることにして。何時だろうと枕元から少し離したところに置いてあるスマフォに手を伸ばす。
「……ん、あれ?」
電話を手に取ってから、ふと違和感に気が付いて小さく首を傾げる。いつもなら触れるはずの彼女の頭部に、触れなかったのだ。さらさらとした髪には触れたものの、形の良い丸い頭部に触れなかった――……そう気が付いて、視線を落とす。いつもと同じ体温。いつもと同じ匂いだから、最初は気付かなかったけれど。クッキーの効果が出たのか、久遠ちゃんは縮んでいた。
すうすうと規則的な寝息を立てて眠りこけるその姿は、いつもと変わらない。でも確かに、彼女の身体は小さくなっていた。表情もどこか、いつものそれよりあどけない。目を閉ざしていても、無垢で純真な様がわかるほど。身体が小さくなったからか、いつもより瞳が占める割合が大きくなっている気がする。
「ふふっ、お口もちいさーい……♡」
食んでしまっている髪をついと指で除けてやりながら、ついそんなことを口にした。ふにふにと指の腹で唇を押してみる。弾力の良いそれは、先ほどまで二指分はゆうにあったのに身体のサイズに応じて縮んだせいか、今は一指分しかなかった。やや口をすぼめている状態になっているのもあるとは思うが、突いている俺の食指の先よりもまだ小さいかもしれない。
「ん、んんー……?」
ちょっかいをかけすぎたのか、穏やかだった寝顔が崩れる。ちいさく眉を寄せて唸り声を上げる様子に、ふふっと笑みをこぼして指を引いた。ゆっくりと持ち上げられた瞼の向こう、陽光を浴びてきらきらと輝く翡翠の瞳が覗く。ぱち、ぱちと何度かその目を瞬いて、もう一度瞼を閉ざすと――最後にゆっくりとまつ毛が持ち上げられる。いつもよりあどけなさを残す表情。くりくりとした大きな瞳がこちらを向いて、ふわりと表情が緩められる。
「……おはようございます、千弘さん」
微笑んだその表情も、はにかんだと表するのが一番近いようなそれで――。彼女がそうであったように、自分自身も《《久遠ちゃんのことなら》》どんな姿になっていようとも愛せるんだな、と実感させられて足元がふわつくような感覚に襲われた。ああ、うん。……幸福感、多幸感ってキミと一緒にいるときのそれを言うんだろうな。
「おはよう、久遠ちゃん」
胸中に去来するさまざまな感情をない混ぜにしたまま、なんとか言葉を紡ぐ。
肉体年齢に色んなものが引っ張られる感覚は、俺自身経験済みだ。だからいくら中身がいつも通りと言っても、細かな差異があるのはわかっていた。けれど。……それにしたって彼女の表情は、最初から柔らかく、かつやさしい。いつもそうと言ってしまえばそうだけど、いつもはもっとふにゃふにゃに蕩けて、蕩けきってからでないとこんな表情にならないのに、ただ起き抜けに愛おしげに俺を見つめて細められた瞳が、もう――蕩けて潤みきっている。全身で俺への好意と幸福を示してくれるときに覗かせるそれなのだ。……俺も、あのときはこんな表情をしていたのだろうか。眩暈がしそうなほどの倒錯感。もしそうだとしたら、彼女があのとき、あれほどまでに照れていた理由もよくわかる。
「ん……?私、なんだかいつもより声高くないですか?」
喉に手を当てて訝しげな表情をする彼女の視線が、喉に当てるために動かした手の方へ注がれる。違和感に気付いたらしい。
「……えっ?な、なんで私縮んでるんですか!?」
至極真っ当な問いかけに、俺は肩を竦めるとちいさく笑って応じた。――「朝、何食べたか覚えてる?」と。その言葉に「あ」と声を上げた彼女のちいさな身体を抱え上げて、そそくさとベッドから出る。時間を、無為にしないために。
◇ ◆ ◇
「ごめんね、久遠ちゃん。……許してくれる?」
顔を洗って軽い食事を摂り、事情――というよりは俺の思いつきの悪戯――をひと通り話した後、そう尋ねた。いつも使っている食卓ではなく、ソファの上でちょんと座った彼女の前で、俺は床に座している。勝手にしたのだから、謝る以上はそうしようと思ったためだ。
「……もう。怒ってないのは、千弘さんなら気付いてますよね?だから謝らなくていいです。座るのも遠慮せず|隣《ここ》にどーぞ。まあ、驚きはしましたけど……。千弘さんが前に提案してくれたアルバムとか、持ってなかったですしね……」
両手で持っていたグラスをローテーブルの上に置きながら、言葉を選ぶようにしてそう言われる。俺の身体が退行したとき、彼女にも幼い頃のアルバムとか見てみたいなぁと言ったことも覚えていたようだ。彼女は大学時代からのひとり暮らしで、|卒業アルバムなど《そういったモノ》の類いは実家にあるのだと、前回申し訳なさそうに話してくれた。
ぶかぶかな服の袖を直しながら困ったように笑う表情は、ちいさくなっても彼女は彼女だとわかるのに十分な表情だった。
いつもころころと変わる表情が、今はさらにころころと変わる。溌剌としているというほど元気なタイプというわけでもなく、控えめなのにくるくると変わる表情を見るのが、俺はなんだか妙に愛しさを覚えるから好きなのだけど。いつもはきっと、そっと俺に気付かれないようにしているのであろう表情の変化も、今はつぶさによく見える。俺がそれに気付いてまた感慨深げな表情をしているのか、くるくる変わる表情の合間に俺の様子をちらりと見やる様や、目があってバツの悪そうな顔、悪戯っぽく破顔して一瞬ぺろりと覗く舌など――堪えるのが大変なほど表情が次々に変わっていく。普段の久遠ちゃんも感情の機微がとても繊細で、そっと俺の考えや声色に寄り添った反応を返してくれる子なのだけれど、今は感情の起伏自体が大きくなっているのだろう。
「……ん、ありがとう」
「もーほら、謝らなくていいって言ったじゃないですか!そのお顔もダメですよ。ほーら千弘さん、いつまでそこに座ってるんですか。|隣《ここ》って言いましたよ!」
ぽふぽふと自身の隣の座面をちいさな手で叩きながら、彼女はむうと頬を膨らませる。いつものその表情も、今の姿でやると本当に子どもの駄々といった感じがして、思わず俺も表情を緩めた。「はぁい」と応じて床から腰を上げると、こちらを見つめる大きな瞳と目が合う。きらきらと好奇心で輝いた瞳に見据えられて、ほんの少し困惑する。俺が何か言う前に「ふふ」と破顔した彼女が、俺がソファへ向かう動きに合わせるようにして、ぴょいとちいさな身体を跳ねさせた。
「えっ、ちょっと……久遠ちゃん!?」
完全にダイブする姿勢の彼女に向かって慌てて手を伸ばすと、待っていたというように身体を預けられる。脇の下に手を回して抱き留めると、そのままソファへ腰を下ろして膝の上へと着地させる。ほっと息を吐くと、悪戯に味を占めた子どものような表情をした彼女が「ふふー」と笑みを浮かべながら、俺の顔を仰ぎ見ていた。
「もう、突然ダイブするからびっくりした……。怪我でもしたらどうするの」
「えー。自分が座ってたところから千弘さんに向かってダイブしただけですよ?下も絨毯ですしへーきです。それになにより、千弘さんなら抱き留めてくれると思ってました♡」
下からすいと伸びてきた手が、ぺたりと頬に添えられる。ちいさな手から伝わる温度が、心地いい。さらさらと背中に流れ落ちる髪を、思わず片手で梳く。
「やーっと申し訳なさそうなお顔じゃなくなりましたね、千弘さん。むしろ、千弘さんがそうして我が儘をぶつけてくれるのが嬉しいんだって……何度言ったら覚えてくれるんですかー」
むいむいと、ちいさな手に頬を揉まれる。かけられた言葉に、悪戯がバレてバツの悪そうな顔をしていたのは俺の方か――と、そっと息を吐く。……本当にこの子には敵わないなぁ。
「……ん、そうだったね。じゃあちゃんと言い直すよ。久遠ちゃんがちいさくなったらどんな感じになるんだろうなって思ったら、どうしても見てみたくって」
トーちゃんの差し入れのジョークグッズ調べて買ってきたの、と言うと「ほんとに普通のクッキーみたいでしたねぇ……」としみじみとした感想が返ってきた。なんというか、彼女は本当にそういうところがちょっと抜けているというか。芯が強いのは知っているのだけど、出会ったときもこの調子で一般企業を騙った悪徳業者の撮影に引っ掛かりかけていたのだから、もう少し警戒心を持ってほしいような気もする。まあ、俺に対して警戒心を抱かずにいてくれるのは、それだけ信頼してくれているんだなと思うからいいんだけど。ちいさく笑って曖昧に返事を濁していると、頬を揉んでいた手がぴたりと止まった。
「そういうわけで、ちひろおにーちゃんのワガママを聞くのは私の特権なので、いーんです!」
そう言ってにっこりと笑った彼女が、背伸びをしてぐっと顔を寄せる。そのまま鼻先に口付けられて、一瞬言葉を失う。いや、俺も自分が退行したときはこんな感じだったから、今のは意趣返しなのだろうけど。
「……久遠ちゃん、実は結構根に持ってたりする……?」
「いいえ?でも、千弘さんも言ってたじゃないですか。〝このカラダだからこそ出来る事……楽しまないと損でしょ〟って」
だから普段のカラダだとできないことをやっておこうかなーと思って、と続いた言葉になるほどねと苦笑した。俺、あのとき余計なこと吹き込んじゃったなぁ……とほんの少しだけ反省する。キミがそうだったように、俺だって《《相手がキミなら弱い》》んだけどなぁ。
「ちひろおにいちゃんが不意を突かれて驚くのは珍しいので♡ この機会にいっぱい拝んでおこうかなーと思っただけです♡」
普段は素直でいじらしさが強い子ではあるけど、そうだった。彼女は俺が《《そう》》していいよと言えば少々強めに出られる子でもある。反対に、俺が求めれば受け手にも徹せる。こういう《《イタズラ》》が好きなのは俺と同じ。仕事じゃなくてただの素で、俺という人間のこれまで知らなかった欲をするりと自然体で引き出せる唯一の相手なのだから。俺が彼女の全部を欲しがるのと同じように、久遠ちゃんも俺の全部を欲してくれているに過ぎない。それが〝俺も知らない、自覚していない新たな欲の芽生え〟であっても……だ。お互いにそうして自然と求めているだけのこと。
――日常において、この手の変化はスパイスだ。だから、俺はあの日も彼女に〝恋人なんだから罪悪感を感じる必要はない〟と言った。これは嘘偽りのない、本心からの言葉。どうせならそのすべてを楽しんでほしいと、俺は素直にそう思っている。いつも全部は言葉にしなくても、そうして接してきたから……彼女にも、その想いは通じているのだろう。だからこそ、余計に敵わないなぁと思うのだけど。
「ふふっ……千弘さんも、結構無防備になってないですか?」
「あは、やっぱりキミには敵わないなぁ……。やっぱり見た目が若返ってると、ちょっと油断しちゃうのかもね」
子ども相手に警戒心を抱くことって普段あんまりないもんねと独り言ちるようにこぼすと、彼女は俺の膝の上で満足げに笑う。そうでしょうと言いたげな表情に、そこはちょっと意地悪を言ったかなぁと俺も眉を下げた。
「……ところで久遠ちゃん、あの……急にどうしたの?」
満足げに笑ったと思いきや、身体の向きを変えて俺に向き合うようにして座った彼女の行動に、思わず問いを投げる。俺のときと同様、普段着ている服を一枚纏っただけのその恰好は、少々危なっかしい。ぶかぶかの服がずり落ちた肩口から、動くたびに白い肌が覗いている。いつも俺の視界の方が高いとは言え、さすがに彼女が腕を伸ばすたびに生まれる隙間から、まだ隆起する前の控えめな双丘やいつもより遙かに肉が薄く、呼吸に合わせて上下する腹部が視界に入るのは……罪悪感があった。わかっていてやっているのだろうか、と若干処遇に悩む。
「んー、いつもとどう変わるのかなぁと思って……。よいしょ、っと……ちょっと失礼しますね、千弘さん♡」
そう言うと、彼女がぎゅうと俺に抱きついてきた。いつもよりもずいぶん小さな、その身体で。いつもは俺の身体全部で抱きしめてあげるその身体も、ちいさくなった今は俺の腹部にくっつくだけで、もうそのほとんどが覆えてしまいそうなほどのちいささだ。そんなちいさな身体でも、俺を真正面から受け入れて――愛そうとしてくれる。
「ふふっ、千弘さんの心音……やっぱり心地いい」
鎖骨の下――タトゥーを刻んだあたりに頬がすり寄せられた。触れた肌から伝わる体温が、心地いい。さらさらと、何度か確かめるように後頭部の髪を梳く。いつもの手触りがして、安堵した。姿形が変わっても、久遠ちゃんだとわかる。いつもよりほんの少し高い体温も、やや早めの拍動も。違っていても、忌避感は湧いてこない。
わずかに躊躇ったあと、ようやくそのちいさな肢体に腕を回した。片腕だけで抱き竦められてしまうほどに、ちいさな身体。その首筋に鼻先を寄せる。……いつものように。嗅ぎ慣れた体臭がして、わかりきっていたはずの〝なにも変わらない〟久遠ちゃん本人だと実感して、ゆるりとなにかが融解していく感覚がする。
「……千弘さんも、罪悪感湧いちゃいましたか?」
ぽんぽんと、ちいさな手で背中をさすりながらそう問いかけられて、答えが紡げなかった。こんな感覚なんだなぁって、自分が退行したときには思わなかったのだ。酷なことをしただろうかと、どうしても不安が湧いた。
普段の彼女は理性的で、倫理的に外れることはまずできない。その精神的なブレーキを外してあげるには、ほんの少しばかり背中を押してあげる必要があった。俺自身、今はじめてこんなにも《《彼女だから》》こそ込み上げてくる衝動が、何ひとつ普段と変わらないことを実感したのだ。
「……今の私も、普段の私も。千弘さんの全身を、抱きしめてあげることはできないですけど……。こうして、千弘さんの腕の中では安心できる、って伝えることならできます。……それに、私だってこれでもめいっぱい、世界でいちばん大好きな人を、カラダ全部でぎゅってしてるつもりです」
――だから、ちゃんと《《今》》の私の表情を見てください。
そう言われて、顔を上げる。そこにあったのは、無邪気な少女のそれではない。あの日垣間見せてくれた、少しお姉さんの表情でもない。いつもより潤んではいるけど、間違いなく。リンゴ色に染まった頬も、とろりと下げられた眉も、俺を見上げる熱のこもった視線も。全部が、見慣れた恋人の表情だった。
「あぁ、もう……またそんな可愛いお顔しちゃって」
〝もっとその可愛いお顔を見せて〟と、あの日をなぞるようにそう応える。そんな顔をされたら、すぐめろめろになって……キミが欲しくなっちゃうんだもん、と告げたときと同じ表情。
「……ん、千弘さん。ちゅう、しましょう?」
そう言うと返事を待たずに、ただ触れるだけのキスが唇に落とされる。ちゅ、と音を立てて離れたあと、ふわりと柔らかな笑みが向けられた。
「カタチが変わっても、私は私です。……千弘さんの、《《恋人の私》》のまま、なんですから……そんなこと気にしないでいいんです」
だって、《《私が、千弘さんとこうしたい》》んですから。――そう言って、あの日の俺と同じように与えられた免罪符。だからもっと、とちいさな口で口端を吸い、ぺろりと舐め上げられる。薄く開いた唇の隙間から、ちいさくて真っ赤な舌が挿し入れられた。ぬる、と普段よりいくらもちいさなそれが、俺の舌先を這っていく。するりと首の後ろに手が回されて、より深いキスに変わった。短くなった舌を、必死に絡めて貪られる。
「ン、……それとも、千弘さんは《《私》》とこういうことするのは、いや……ですか?」
ぷは、と息継ぎの合間に途切れがちに。潤んですっかり夢中になった瞳が、こちらを見てそう問いかける。
「……そんなこと、あるわけないよ」
……でも、だからこそ怖い。俺が退行したときは、キミが受け入れてさえくれれば、あとの問題は些末なものだった。ただ、俺が頑張ればいいだけの話で済む。職業柄テクニックはあるし、ほとんど毎日のように求めても飽くことのない彼女の身体のイイところは、本人以上に覚えている。なにより彼女に快感から感じ方まで、その全部を教えたのは俺だ。現時点で貰える全部を貰って、その上でまた染め上げて。……それで良かった。けれど彼女が退行するとなったら、話は変わってくる。俺自身が、どこまで耐えられるかわからない以上、簡単にYESを返すわけにはいかない。
「……怖い、ですよね」
ぽつ、と至近距離で瞳を覗き込んで、たったひと言。
なにがとも言わずに、ただそれだけ。愛おしみ、慈しむ表情で……そう問われる。やさしく凪いだ声音は、俺を責める意図などないことを表していた。
返事を返せずにいる間に、する、と伸びてきた手折れそうなほどに細い腕が俺の頭を撫でていく。彼女の胸元に当てられた耳が、慣れ親しんだ鼓動を拾った。全身で包み込まれて、その温かさに弛緩する。
「たしかに、今の私では挿れるのは無理かもしれません。……でも、一瞬に良くなる方法はそれだけじゃないって、教えてくれたのも千弘さんですよ?」
くすっと笑って、気軽に言ってのけられた言葉。ほんとに、もうちょっと危機感を持った方がいいんじゃないかなぁと思うくらいに、あっけらかんと。目が眩んでしまいそうなほどに、眩しくて。迷子になってしまっていた俺の想いを、まっすぐ照らして引っ張ってくれるのは……結局、いつもキミのその笑顔と、全部を受け入れてくれる安心感なんだなぁと、思い知らされる。
「……あは、そうだったね。それに、その分元に戻ったら俺の全部、久遠ちゃんに責任持って受け留めてもらえばいっかぁ……♡」
彼女が遠慮しなくていいと言うのなら、気兼ねなく。今を楽しく、今しか味わえない感情も快感も、全部をふたりで共有しよう。スイッチを切り替えると、俯いて顔にかかった髪を掻き上げながら、ぺろりと舌舐めずりをする。ゾクゾクと、腹の底から這い上がってくるような快楽の種を予感して、身体が準備を始めたのがわかった。……久遠ちゃんの方も、同じ。俺のこの動作は、最早ふたりの間で共通の認識の《《意味》》を持つ動作になっているからだ。
期待にその瞳の色を蕩して、熱を持ち潤んだ視線が一層熱を増す。かわいいかわいい、俺に食べられることを期待して、燻る熱に身を焦がして——与えられる刺激と快楽を待ち望んで、受け入れる準備を始めた顔。俺が与えるそれでなくては満足できなくさせられた彼女の、俺にしか見せない表情。
「千弘、さん……」
期待にちいさく喉を震わせた声が、甘さを増して俺の名を紡ぐ。その声だけではやくほしい、と言外に強請られて、くつくつと笑いが漏れてしまいそうになる。
「ふふっ、順番に……ね♡ まずはお口あーんってして、もっとちゅうしよ?」
髪の房を避けるように耳に掛けながらそう声をかければ、大人しく眼前でそのちいさな口が開かれた。
「ん、素直でいい子♡」
言い切らぬうちに舌をその咥内に滑り込ませると、歯茎と歯列をなぞっていく。いつもより狭くちいさくなっている咥内は、俺の舌を挿し入れただけでもういっぱいになってしまうほどだった。ただでさえ薄い舌がさらに薄くなって、舌先の神経が敏感になっている。わかっていて舌を絡め取ると、根元まで弱い箇所……神経の集中しているところを重点的に嬲りながら舐め上げた。ひくりと震える喉の動きを逃がさないように、呼吸ごと貪るように音を立てて舌を吸う。吸った舌がぢゅう、とひと際大きな音を立て、酸素を求めて喘ぐ動作に合わせ、一度緩めてやる。鼻から取り入れた分だけでは到底足りずにぼんやりと視界を揺らがせる彼女が、流れ込んだ酸素を必死に取り込もうと薄く口を開閉させた。長さも大きさも、質量からして違うモノを受け入れているのだから、当然と言えば当然なのだが、たったそれだけで双眸がとろとろに蕩けてしまっている。
ただでさえ開発されて弱くなった咥内を、ほとんど一度になす術もなく食い荒らされたのだから、仕方のないことではあるが。肉体年齢に引っ張られて、いつもより《《堪えられない》》ことを、俺は身をもって知っていた。生理的に浮かんだ涙を目の淵いっぱいに溜めて、肩で息を繰り返す。その一瞬だけ間を置いて、無遠慮に角度を変えてもう一度貪った。
「ン、んぅ……」
堪えきれず、鼻先から吐息が抜けていく。上顎から喉奥にかけて、ワザと舌のざらつきを引っ掛けるようにして舐めてやると、首に回されていた腕がちいさく震えてひくひくと呼応するように、喉が数度痙攣する。
絡めた舌裏を撫で上げながら、混ざった唾液を嚥下するようにして口を離す。
「ぷは……っ、ぁ……♡ はー、はぁっ……♡ しゅご♡ ちひろさ、ぃまの……なにぃ……♡」
ひぅひぅと喉を鳴らして喘鳴とともにそう言われて、思わず笑みが深まった。本人も予想していなかったのだろう。今の一瞬で完全に思考がぽやぽやと飛んでしまっているのが見て取れる。
「あは、久遠ちゃん……キスだけで軽くイっちゃった?」
「ん、はい……。頭ふわふわする……♡」
酸素不足と弾けた快感に、脳髄が痺れるような感覚に囚われたまま。ゆるゆると頭を振ってそう返事を寄越した彼女のふやけた声が、耳朶をくすぐる。
「ふふっ、そっか♡ もー、ほんとに快感に素直でかわいーなぁ……♡」
ふわふわと視線が浮ついたままなのは、表情を見ればよくわかった。くたりと預けてきた身体を抱きしめ、頭を撫でる。気持ちよさそうに細められた目が、こちらを見上げて、さらに表情が緩んだ。ふわり、と。花開くような笑みを浮かべて、甘えるように頭をすり寄せられる。
「ふふー、千弘さんになでなでしてもらうの、すきです……♡」
なんだか落ち着くんですよねぇ、と話しながらくすくすとちいさく笑って。ひと心地ついてすっかり力の抜けている背を撫でた。……まだ燻っている熱に、火を点けるように。ちいさく跳ねた肩を見て、ほらやっぱり、と内心で笑う。たった一度イったくらいで満足できないことくらい、よく知っている。
「ひとりで気持ちよくなってないで、俺のことも満足させてね?」
煽るようにそう言って、軽く頬に口付けた。ぽっと一瞬で真っ赤に染まって熱を持つそれに、頬ずりをして。薄い腹部に、ぐりと俺の熱を押しつける。困ったように眉を下げた彼女が、こくんとちいさく頷くのを見て、じわじわと迫り上がってくる焦燥を、必死に抑えた。
「ふふ、想像しちゃった?久遠ちゃん、俺のこれだぁいすきだもんね?キスだけでイっちゃうくらい快感に弱くて、敏感になってるそのちっちゃなお口で、こーれ、奥まで咥えたらどうなっちゃうかなぁ♡ 試してみよっか?」
すりすりと、押しつけたままのそれを服の上から指でなぞって、さらに意識を高めさせて。ほんの少し意地悪にそう聞くだけで、糾弾するような涙目が俺の瞳を見据える。ただ、その視線は糾弾であって糾弾ではない。そんな風に焦らさないで早く欲しい、と言葉にしない彼女の|要求《おねだり》だ。
「あは、物欲しそうな目しちゃってるね♡ 久遠ちゃん、もしかしてもう俺の、ほしいの?」
敢えて焦らして、そう尋ねる。本当は、早く夢中に乱れる様を、誰よりも見たいけれど。――限界まで高めてあげた方が、彼女の色香は濃く花開くから。無意識に喉を鳴らして、あと一歩のところで誘惑に耐えて踏ん張っているその表情が、背中を押されて堕ちてくるところを……何度でも見ていたい。
「……っ、ほしい、です」
酩酊して呂律が回らなくなるような錯覚がするほど、互いに溺れられるように。一番良くなる方法を、その日ごとに選びながら……なんて。御託の上ではそうだけど、ただ、俺が〝俺で乱れる〟彼女を見るのが、好きなだけ。欲求を抑えられずに唇を湿らせる、赤い舌先をちらと視線で追う。あの舌で、口で愛されて求められるときの快感を、俺の身体ももうすっかり覚えてしまっている。衝動が疼いて、止まらない。ぺろり、と。ご馳走を前にして焦れる気持ちを抑えながら、いつものように言葉を引き出す。
「ほんとに素直だねー……。久遠ちゃんのお口に、俺のなにがほしいの?」
「千弘さんの、おちんぽ……私のお口にください……♡」
ひと呼吸の間もなく、要求通りにおねだりをして口を開いてみせる様に、喉奥が鳴る。
「よく言えました♡ それじゃ、そのお口に咥えていーよ。あ、でも普段の身体じゃないんだから、無理はしないこと。いーい?」
「はぁーい……♡」
ちいさな手がジッパーにかけられて、ぞくぞくと背徳感が背筋を駆けのぼっていく。ぴりぴりと淡い電流で嬲られるような感覚に、身を委ねて手慣れた手つきで俺のそれに愛おしげに口を寄せる顔を、くいと上向けた。
「ちゃーんと、俺のおちんぽしゃぶってる、えっちなお顔も見せて♡」
上から見据えた俺の視線を、彼女が逸らせなくなったのを確認して。まだこんなにちいさな外見でも、ここまでとろとろに蕩けた表情ができるんだなぁ、と。お菓子の効果が切れるまで、高めて高めて……極限まで高めて、それから元に戻ったときに、ようやく焦らしに焦らされた欲望を、最奥に穿たれて善がる様を見れるまで、朝一度俺を受け入れたあとの彼女が、耐えられるかなぁ……と。
――期待と羨望と、どろどろと溶けて混じった欲を乗せた熱い吐息を、ひとつ吐いた。
多分、彼女は拒絶しないだろう。こんな機会はなかなかないし、試してみようとそっと心に決めて、彼女がくれる身を焦がすような快楽を、俺もいっしょに享受ことにする。
このまま、気持ちいいことだけで頭の中がぐちゃぐちゃになるくらい。互いに乱れる時間も、俺たちにとっては〝しあわせ〟だから。
目次へ戻る
2022年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
怠惰
2022/04/25
――千弘さんは、とにかく甘い。際限なく甘やかしてくるので、つい甘えてしまう。ある程度は自分でやろう、と思っていても……見透かしたかのように、やっておくよと言ってしまうのだ。
しかも、こちらに罪悪感を抱かせないようにするのが上手い。「代わりにこれをお願いしていい?」と提案されてしまうと、強く突っぱねることも出来なくなってしまう。
「……むぅーん……」
千弘さんが家事をしているのを、ソファで横になりながらぼんやりと見守ってちいさく唸る。千弘さん本人に、聞こえないくらいの声量で。
普段から忙しい人ではあるのだけど、ここしばらくは撮影の本数が本当に多くて、一日仕事のことも多かったのだ。ようやくそのラッシュが落ち着いて、久々の連休が、今日からだった。昨日もなんだかんだ二本撮りだったのに、帰って来て早々に「明日はお休みだしいいよね?」と求められた――結果、今日の私は腰が立たない。……というより、起きあがろうとしたら本当にかっくりと力が抜けてしまって、以降千弘さんに絶対安静を言い渡されている。
――ええ、はい。油断してました……。どこにそんな精力が?と疑問に思うのはいつものことにしても、お仕事が忙しくなると、千弘さんは回数や量を完全にコントロールに入るので、ほとんど毎日したとしても、《《いつもよりあっさり》》終わらせる。それが比較的長期間続いていたので、完全に油断していました。はい……、だって私がイかされる回数は普段と変わりないんだもん……。気付かなくても許してほしい。そのくらい自然に調整されるんです。……と、誰に向けるでもない思考の中で、思わず言い訳をする。
せっかくのお休みなのに、千弘さんにばかり家事をさせるのは……と交渉を粘ってもみたのだけど、取り付く島すらもらえず。お天気いいからお布団干しちゃうね、と抱っこで抱えられてソファに移されたまま甲斐甲斐しく世話を焼かれている。しかもちょっぴり、世話を焼く千弘さんが楽しそうで……余計に食い下がりづらい。
「よし、こっちは片付け終わったよー♡ 久遠ちゃんは腰の調子、どーぉ?」
「……お疲れ様です、すみません千弘さん……。腰、は……うぅん、まだわかんないです……!」
痛みは元からほとんどない。ぎっくり腰とかとは違って、本当に力が上手く入らない、と言った感覚が近い。だからこそ、横になっていると自分でも治ったかどうかがわからなかった。
「うーん、そっかぁ。……一回、ちょっと身体起こしてみる?」
「……そうしてみます。千弘さんごめんなさい、手……借りてもいいですか?」
「もちろんいいよ、でも無理はしちゃダメだからね?」
「……はぁい」
そう言って差し出された手を取る。ぐぐ、と力を入れて上体を起こすと、なんとか起き上がれそうだった。
「あ、ちょっとマシになった……かな?」
「んー、でもまだちょっとつらそうだね。久遠ちゃん、起き上がるときに結構力入れたでしょ?」
図星を突かれて言葉に詰まる。くすくすと小さく笑った千弘さんが「手繋いでるんだもん、わかるよ♡」と言う。まだ動いてはいけないとの判断に、しょんぼりとして千弘さんの顔を見上げると、やさしく微笑んで空いた手で頭を撫でられた。
「今日はお家で大人しくしてよっか♡ あと、久遠ちゃんには今から俺の抱き枕になってもらっちゃいます……♡」
そう言って、するりと繋いだ手がやんわりと解かれると、膝裏と背中に腕が回されて、そのまま抱きかかえられる。
「え、え……?千弘さん……!?」
「ほーら、いい子にしてないと落ちちゃうよ?」
スタスタと迷いなく寝室への道を進まれて、混乱しながらもその首に手を回してしがみついた。
「お布団も干したばっかりだから、ふわふわで気持ちいーし♡ やることないから、お昼寝でもしよ?俺が一番ぐっすり眠れるのは、久遠ちゃんをぎゅうってしてるときだからさ♡」
ぽすんとベッドに下ろしながらそんな風に言われて、断れるはずがないのにズルいなぁと苦笑する。
「……わかりました、お昼寝……お付き合いします♡」
「やったー♡ じゃあさっそく……♡ ぎゅう〜……♡」
間髪入れずに抱きつかれて、お腹の辺りに顔を擦り寄せられる。意識してしまって、正直それどころではないのだけど。
「……ふふっ、安心して♡ 今は、手を出さないから……ね♡」
「い、今は……!?」
素っ頓狂な声を上げた私を嘲笑うかのように、千弘さんが問答無用で身体をひき倒す。背中にベッドの感触がして、ほとんど無意識に千弘さんの顔を盗み見た。
「ふふっ、期待しちゃった?今はとりあえずもう一回寝ようね♡」
ズルいなぁ、と思いながら抱き着いたままの千弘さんの頭を撫でる。ふわふわの気持ちいい髪質に、思わず目を細めた。
「……おやすみ、久遠ちゃん♡」
「……おやすみなさい、千弘さん♡」
そう挨拶を交わして、安心する温もりに――意識を手放すのは、そう時間はかからなかった。
目次へ戻る
読上
退路
2022/04/22
「千弘さんっ」
とたとたと軽快な足音とともに、名前を呼ばれて振り返る。ゆるっとした部屋着に身を包んだ久遠ちゃんが、こちらへ走ってきていた。
「ふふ、どうしたの?」
今日は彼女が学生時代の友人たちと出掛ける用があって、先ほど帰宅したばかりの彼女を「ひとりでゆっくり入っておいで」とお風呂に送り出した後だった。乾かしたばかりの髪が揺れて、いつも以上に色濃く桃の香りがする。俺と同じものを使っているはずのそれが、彼女の体臭と混ざってより甘く濃い匂いを香らせるときの、記憶が脳裏にチラつく。なるべく疲れていそうな日は手を出さない、と自制しているつもりなのだけど……すっかりこの日々で根付いたそれらの反復記憶に、最近はかなり簡単に理性を持っていかれそうになる。
「お料理中にごめんなさい……!千弘さん、ちょっとだけ屈んでもらえませんか?」
「ん?うん、これでいいかな……久遠ちゃん?」
請われるままに屈んで視線を合わせると、不意に顔が近づいた。……そのまま、躊躇いなく唇を合わせられる。食むようにして柔らかく唇で挟まれて、ようやくその唇にリップクリームが塗られているらしいことに気がつく。
「……ん、よし♡ ふふっ、ありがとうございました千弘さん♡ ちょっとリップクリームつけすぎてしまって……」
満足げな表情で離れてそう笑った彼女に、俺は不意打ちを受けてキョトンとした表情のまま見つめ返す。日常的によくキスはするけれど、大体《《応じる側》》の彼女から、おねだりもなしにしてくれることは、案外少ない。
別にそれでも不満はないし、俺とするキスは好きでいてくれるから、満足していたのだけど。本当に何気なく。ハンドクリームを分けるために、手を取って塗り込むくらいの何気なさで、無邪気にくり出されたそれに、思わず面食らってしまったのだ。
「……あ、あれ?千弘さん……?」
俺の表情を不審に思ったのか、不安そうな表情で薄くて色艶の良い唇が、俺の名前を紡いで。そうして自分が《《何をしたのか》》、ようやく理解が追いついたらしい久遠ちゃんの顔が、みるみるうちに真っ赤に染まっていく。
「……わ、あの……ちが、違うんです……っ!これはその、うっかりと言いますか……っ!」
「あーもう、うっかり無意識でそんなことしちゃうとか、ほんとかわいー……♡ それだけ焦ってる、ってことは……久遠ちゃんにも俺を煽った自覚、あるよね?」
逃げられないように腰に手を回して抱き寄せると、わざと耳元で囁いてみせる。ちいさく身を震わせて、ただ《《囁かれているだけ》》で感じてしまう世界で一番大好きな恋人を、ひょいと抱き上げた。
――行き先は、決まりきっている。
「あのっ、千弘さん……っ!ご飯はどうするんですか?」
慌てて首に手を回して抱き着いてきた彼女が、最後の抵抗のようにそう問いかけてきた。
「そりゃあ、一番美味しいときに食べてもらいたいけど……でも、今日はそんなの後回しでいいよ♡」
うぅ……とちいさく呻いた彼女の耳元に、もう一度甘やかな囁きを落として。
「今いっちばん味わいたいのは、久遠ちゃんだからさ……♡」
「〰〰……ッ♡」
わかりやすく震えた彼女の瞳の色が、期待を孕んだ色になっているのを確認してから。責任取ってね、と言い添えて俺は柔らかにその退路を断った。
目次へ戻る
読上
気付き
2022/04/06
「どうかした、久遠ちゃん?」
いつもと若干様子の違う彼女に、そう声を掛ける。緩慢な動作で、こちらに視線を寄越すと、瞳がようやく朧げに焦点を結んだ。
「ん……、ちょっと……気になって」
歯切れ悪くそう言ったあと、久遠ちゃんは逸らすようにじわりと視線を外す。目で追いかければ、先ほどから流しっぱなしになっているテレビの方に向けられる。――その画面に映し出されているのは、俺の|生業《お仕事》であるAVだ。しかも、割合良く久遠ちゃんと見る機会の多い資料映像ではなく、紛うことなき《《俺の出演作》》。
「ん、気に触ることでもあった?……一旦、止めようか?」
聞き分けが良すぎるきらいのある彼女が、途中でこういう風に言い出すのは珍しい。……というよりも初めてのことで、思わず慰めるように恋人の頭を撫でて、ほとんど反射でそう聞いた。
彼女――久遠ちゃんは、普段はこれ以上ないくらいに、俺のお仕事に協力的な子だ。さすがに嫌だろうからと、やや過激な内容に分類される出演作のチェックは彼女の前では避けてはいたけど、そうじゃない俺の出演作は、《《ふたりで見ることが常なくらい》》に、理解がある。
いつだったかトーちゃんや岡持っちゃんにその話をしたら、揃って呆然としたあとで「久遠さんに感謝すべき」と口酸っぱく言い含められたほどだ。俺としても、資料映像の確認から、それと同じ内容のプレイまで付き合った上で、恋人の出演作を平常心で見られる〝《《普通の》》〟女の子は、後にも先にも彼女だけだろうと思う。
……今日かけていたのは、そこまで過激な内容というわけでもないかもしれないけど、これまでなら俺ひとりで目を通していたような内容だった。やっぱり気分のいいものじゃなかったかな、と眉を下げる。彼女の寛大さに甘えすぎていたかもしれない。「ごめんね」と薄く唇だけで呟いて手を伸ばし、リモコンを取るためにすこし体勢を変えようとした――ときだった。
「待って、千弘さん……そうじゃ、なくて」
慌てたように追い縋ってきた小さな手が、俺の手首を掴む。視線を下げると、気まずそうに眉を下げて、「ええと」と言い淀む彼女と目が合った。
「いいよ、なんでも言ってほしい」
もう片方の手で、形の良い頭をあやすように撫でる。その間にそっと息を吐いて、俺自身の心の準備も整えてから、ようやく尋ねた。
「どうしたの、久遠ちゃん。嫌……だった、かな。こういうの、一緒に見るのはさすがに」
そう言って、俺も視線をテレビ画面に移す。それなりの大きさのモニターいっぱいに、映し出される俺と女優さんの姿。出演作のチェックを名目にしてはいるけど、どうせ初見の内容はもう一度落ち着いて目を通すか、すでに一度目を通したあとの作品だ。資料映像のように、内容をそのままなぞることすらしない。彼女は俺の恋人で、仕事相手ではない。だから俺も〝演じる〟ことはしていない。彼女が《《一番乱れてくれるように》》、そのときどきで変えてはいるけれど。他の人からすれば、なにが違うのだと言われても仕方のないようなこだわり。
――俺のエゴ。
「ちが……っ、あの!千弘さんっ、違うんです……!」
真っ赤に染まった頬が、さらに朱を増す。想定していた反応と違うそれが返ってきて、わずかに戸惑う。頭を撫でていた手を、そのまま頬に下ろして肌に触れた。……あたたかい。よく知っている体温が、肌から伝わる。
久遠ちゃんはそういう職業のプロじゃないから、素直な反応が体温や鼓動に出る。俺だって、彼女とするときはそうだ。映像では伝わらない、鼓動だけが――演技か本心かを、ただひとり、伝えたい相手だけに伝えてくれる。
「……嫌じゃ、ない?」
思わず、ぽろりと言葉が溢れる。子どもが悪戯を咎めた親に尋ねるような響きを伴って落ちた言葉に、久遠ちゃんの視線がこちらに向けられた。その目が、やさしく細められる。手首に添えられたままになっていた手が、するりと肌を撫でて、指先を絡めるように繋がれた。もう一方の手が、ややあって伸ばされて俺がしているのと同じように、頬に触れる。ふわりと笑って、彼女があやすように言葉を紡ぐ。
「嫌じゃないです。……泣きそうな顔、しなくてもいいんですよ。千弘さん」
指先で、愛おしむように肌を撫でられて。無意識のうちに強張っていた表情筋が、ほっと弛むのを感じた。
「……不安にさせて、ごめんなさい。今見てたの、その……普段は千弘さんがひとりで確認してるような内容の、って言ってました、よね……?」
躊躇いがちにそう質問されて、意図を図りかねたまま、俺は「うん」と頷いた。
「……あの、気のせいだったりしたら、忘れてほしいんですけど……」
――そう前置きをしてから、ひと呼吸置いて。久遠ちゃんが、ようやく続く言葉を口にする。
「あの……、これって、普段……その、してること……じゃないのかな、って……」
思ってですね、と口の中でもごもごと紡がれた音。虚を突かれて、一瞬ぱちくりと瞬きをしてから、俺は思わず笑った。
「ああ、ふふっ……♡ なぁんだ、そんなこと気にしてたの、久遠ちゃん?」
「そんなこと……!?私、結構真剣にあれ?って思ったんですよ……?」
「ふふっ、忘れちゃってるみたいだから、特別にもう一回言ってあげる♡ ……〝俺たちだっていつもおんなじようなコトしてるのに〟って、前に言ったの……そういうコトだよ♡」
年末の大掃除中にも、事務所からもらった特殊プレイのAVのパッケージを見て、固まっていた久遠ちゃんに同じことを言ったことがある。彼女もすぐにそれを思い出したのか、これ以上ないほどに顔を真っ赤にした。――まあ、そのとき見つけた|AVの内容《特殊プレイ》をなぞるようにして抱かれたのだから、自分がされていることが|普通のコト《ノーマル》ではない、という自覚はあっただろうけれど。
……ただ。今日彼女に見せているのは、調教モノの内容だったし、言いたくなる気持ちも汲んであげるけど。
「な……っ、え……?」
混乱して言葉が出てこなくなった彼女が、必死に言われた意味を咀嚼しようと眉を寄せて、百面相をする様を上から眺めて。下手な不安なんて、久遠ちゃんの前ではいらないんだな……と、自身の認識をもう一度改める。
「あれ、久遠ちゃんは俺にこうされるのだーいすきだし、壊されちゃってもいいんでしょ?」
最近、輪をかけて強くなった気持ちを、同じだけ彼女が向けてくれていることを確認したくて。何度か尋ねたそれと、同じことをまた問いかける。
「……千弘さん、いじわるですね……。そう言っておいて、壊してくれないのに……」
むうと膨れた頬が、彼女の不満を主張する。けれどそれも長く続かないことを、俺はもう知っているから。
「でもまあ、調教してるつもりはないよ。俺はただ、久遠ちゃんとふたりで、もーっと気持ち良くなりたいだーけ……♡」
――言った内容は事実だ。たしかにほとんど調教だろうと言われれば《《そう》》ではあるけど、俺にそのつもりはない。最初に彼女に言った通り、俺は俺のすべてをもって愛して、愛して……〝この世でいちばん、天国に近いトコ〟に連れて行ってあげたいだけなのだ。最初からそれは変わっていない。変化があったとするならば、元々素直に快感を受け止めることができた俺の恋人の身体が、さらに深く――より強い快感を受け止められるようになった、ということ。俺が、久遠ちゃんのことを〝いつかこの手から離れて行ってしまう存在〟として捉えていたのが、いつしか〝何があっても手放したくない存在〟として《《誰にも渡さないこと》》と、《《解放してあげないこと》》を決めたこと。俺たちふたりがお互い、互いのことをもっと知りたいと欲張りになって求めるようになったこと――くらいで。
気が散って忘れていたであろう、膣内の存在を主張させるように彼女の好きな場所にぐり、と押し付ける。驚いて声を上げ、白い喉元を晒すように背を反らした、自分よりも遥かに小さくて細い肢体を、全身の圧で押さえるようにもう一度見下ろして。にこり、と微笑みかけた。
「……ね、これからもずっと、一緒に気持ち良くなってくれる?」
「千弘さんが……天国に。連れて行ってくれる、んですよね?」
――珍しく、甘えるような声音でそう問われて。〝してやられたなぁ〟と、喉奥で笑う。
「そうだよ♡ ……今の久遠ちゃんなら、前より天国に近いトコにいるの、わかるでしょ?」
そう言って、耳元に口付けると耳朶を食むようにして囁いた。
〝今目の前にいる俺だけに、集中してて〟――と。
目次へ戻る
読上
異世界
2022/04/03
「えっ、なんですかここ……?」
のどかな風景――を通り越して、殺風景とも言える風景が広がる様子に、思わずそう声を上げた。
「どこかなぁ……。その感じだと、久遠ちゃんも見覚えないよね?」
「ない、ですね……」
視界いっぱいの緑に、抜けるような青空。いきなり森のただなかに放り出された訳の分からない状況にも、まあこれだけ平和そうならなんとかなるか……と思えてくる。要は気が抜けてしまうほどの〝何もなさ〟というワケだ。もう一度周囲を見回して、人の気配に神経を集中させる。やはり、人の気配は感じられない。田舎なら特段不思議な光景でもないか、と納得して隣の恋人へ手を差し出した。
「突っ立ってるのもなんだし、ちょっと歩いてみよっか♡」
そんなに危険はなさそうだし、と告げた俺の言葉にこくりと頷いて彼女が手を握り返してきたのが、数十分前のこと――……。
◇ ◆ ◇
「ごめんね、久遠ちゃん。さすがに俺もこれは予想してなかったって言うか……」
――あの後、しばらく森を歩いたところで、彼女が何かを踏みつけた。不思議な感覚が足裏から伝わったのか、「ふえ!?」と声を漏らした彼女にどうしたのか尋ねようと思った瞬間には、うぞうぞと蠢く《《ナニカ》》が久遠ちゃんの周りを取り囲んでいた。隣にいたものの、その生物を踏まなかった俺には一切の興味を示さずに、だ。
「千弘さ、ゃ……これっ、なん……ですか……っ」
目に涙を溜めて、途切れ途切れに聞いてくる彼女の声は、上擦っている。もちろん顔も赤いし、息も上がってしまっている。それもそうだろう。彼女が踏みつけて、吊し上げられたのは——いわゆる触手だった。
さすがに俺も年間300〜400ペースでそういう作品に出ている以上、特殊設定の作品に出ることもあるから、知識としては知っている。〝《《異世界モノ》》〟でお馴染みの、アレだ。……つまるところ、逆説的に今いるここが異世界だということになるけど。不思議なこともあるモノだなぁ、と謎の感慨を抱きながら、目の前で身体をまさぐられて涙目になっている彼女を視界に入れて俺は微笑みを返す。
「あ、そっか久遠ちゃんはあんまりこういうの知らないんだっけ?触手、って聞いたことある?」
「聞き覚え、くらいは……あります、けど……っ!ひゃ……っ、ぁ……♡」
身動きが取れないわけではない。触手の拘束は緩い。けど、足のつかない位置に吊り上げられているせいで、抵抗できずにいる彼女を眺めて「なるほど」と頷いた。
「あの、千弘さ……っ♡ たすけて、くださ……い」
ぴくぴくと小さく体を震えさせて、都度途切れる声でそう請われる。一歩近づくと、真っ赤に染まった久遠ちゃんの顔を覗き込む。
「そうは言っても、こんな弱い刺激じゃイケないでしょ?久遠ちゃんは♡」
なにしろ普段相手をしているのが、俺なのだ。刺激に身を捩ってはいるけれど、彼女がつらいのはむしろ《《いいところを的確に責めてもらえない》》方だろう。自慢ではないが、特技の〝性感帯当て〟はかなりの精度の自負がある。なによりその俺が、徐々に感じ方を含めて……ほぼ毎日、快楽も快感も教え込んできた相手なのだ。並大抵の相手でイケるわけがない。残念ながらこの触手の催淫効果は薄いのか、むしろ感度を上げる方向性の効果にしてあげた方がよかった気さえする。
「な……っ!?千弘さん、なに……言って……!」
――ほら、ね。
触手に責められて、より俺にそれを言い当てられた方がまだ顔が赤くなるんだもん。
「ふふっ、久遠ちゃんの身体の具合で、俺がわからないワケないでしょ……♡ それよりも、俺的にはちょーっと残念だったなぁ、触手ってもっと万能のエロアイテムだと思ってたんだけど♡」
ついついと、指先で彼女の肌の上を這い回るそれをつついて笑う。見た目は様々、凶悪な見た目をしたモノも幾つかあるにはあったけど、イイトコロを責めなければそれすらも宝の持ち腐れでしかない。
頬を強張らせた久遠ちゃんが、抗議にならない抗議を音にできないまま、ぱくぱくと口を開閉させているのも無視して、すり……と上気した頬をひと撫でした。こちらへ向けられた視線を真正面から見据えて、絡めて。とろ、とわずかに瞼が落ちたのを見て、喉を鳴らして舌舐めずりをする。
「ね、イケないのに嬲られてしんどかったよね……♡ 久遠ちゃん、どうしよっか?」
「千弘さ、ん……に、楽に……して、ほしい……です……っ」
「よく言えました♡ じゃあ……久遠ちゃんの望み通りに、ね♡」
そう言って、にこりと笑いかけると手を伸ばした――……。
◇ ◆ ◇
へたりと力の抜けた久遠ちゃんの身体を抱き留めたところで、急に世界が暗転する。
ここへ来た時と同じ。つまり、元に戻してくれるってことかな……と思考しながら、強く彼女の身体を抱きしめた。息を整えていた久遠ちゃんが、そのまま俺の胸元に頭を預けて大人しくしているのを見下ろして、くすくすと笑う。
普段、あんまりモノを使ったりしないからうっすらわかってはいても、自覚は薄かったと思うのだけど。どれだけ俺のいいように染められているのか、さすがに彼女にも伝わっただろうなと思って逆に楽しくなっている。多分、彼女はもうずっと前から知っていて。それでも、俺相手だからいいかと色々と赦してきてくれたはずだから。
……暗転した世界に、光が射してくる。それは、俺が彼女の存在に救われて一筋の光明を見つけたあの日の感覚に、よく似ていた。
『……なんで、謝るんですか』
キミのことが好きだよと告げた俺が、そのまま最後に『ごめんね?』と言い添えたのを聞いて告白の返事よりも先に、彼女が返してくれた言葉。それに俺は『俺のお仕事、嫌って子もいるでしょ?』と答えた。そして『無理に俺の事好きになれ、なんて言わないよ。でも、俺は久遠ちゃんのことが好き』——、そう言った。
言いはしたけど、多分あの時からずっと……手放す気なんてなかったよなぁと、自分のことを自分でもすこし懐かしく思いながら思い出す。まあ、俺も別に俺のことを彼女が嫌っていない――どころか、割と好意を持ってくれているのは知ってたんだけど。でも、だからこそ。本当に言葉の通り、《《俺にならいい》》と思ってまるごと受け入れてくれているんだなとわかったら、より愛しさが溢れて止まらないんだ。
ぶわっとひときわ強い風が吹き抜けて、思わず目を瞑る。次に目を開けたときには、見慣れた部屋が広がっていた。飛ばされる前、談笑していたはずのソファにそのまま戻っている。
――俺たちが生活をしている家。ふたりの家。無機質で最低限しか物がなかった部屋は、今では彼女との生活でできた思い出の数々があちこちに飾ってある。華美さはなくても、どこを見渡しても久遠ちゃんとの思い出が蘇る、そんな家になった。
「あ、あれ……お家に戻ってる……?」
腕の中でそう声を上げた彼女は、なんだったんだろうとしきりに首を傾げている様子だった。一度体温が上がったせいか、甘くて落ち着く……俺の大好きな香りがふわふわと鼻腔をくすぐってくる。
「無事に戻れてよかったね、久遠ちゃん♡」
なでなでと頭を撫でながらそう言うと、大きな瞳がこちらを見上げて細められた。
「ほんとに……いきなり捕まったときはどうなるかと思いましたけど……」
ごにょごにょと視線を逸らしながらそう言った彼女の言葉尻が、どんどんと萎んでいく。俺の前では臆面もなく乱れてるのにと。意地悪なことを言おうかと思ったけど、それもやめて視線を彷徨わせている久遠ちゃんの耳元に、唇を寄せた。
「でも、俺は嬉しかったよ……♡ ただ、俺はシてないし……不完全燃焼なんだよね♡」
そう囁くと、触れそうな位置にある彼女の耳が、瞬く間に真っ赤に染まる。じわ、と熱い体温が触れていなくても伝わってくる。
「ねぇ、久遠ちゃんも一回イったくらいじゃ満足できないでしょ?」
というわけで、と言いながら身体をやさしく座面に引き倒すと片手で服を脱ぎ捨てて、久遠ちゃんに覆い被さった。
目次へ戻る
2022年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
融解する温度
2022/03/12
「千弘さん、何してるんですか?」
ひょいと背後から覗き込むように顔を出した彼女の声に応じるように、そちらへ視線をやる。すぐ傍にやってきた横顔が、興味津々といった表情で思わず口元を緩めた。
彼女の動きに合わせて、さらさらと揺れて落ちた髪が首筋をくすぐっていく。自然と、安心しきって寄ってきてくれる彼女の無自覚な信頼に、それだけで満たされていく感覚がする。
「ふふっ、この間の写真をちょっとね、見返してて」
「……あ、プラスタの更新ですか?」
「ううん、ほら。約束したけどなんだかんだでまだ送ってなかったでしょ、写真」
「ん……っ、そうでした……」
その日のことを思い出したのかさっと頬を朱に染めたその表情も、とてもいじらしくて。くすくすと、つい笑みが漏れた。すこしだけ眉尻を下げて、咎めるような表情をした久遠ちゃんがこちらを向いて頬を膨らませる。くるくる、ころころと変わる表情が……俺の前でだけなんだと思うと、こんなにも愛おしい。出逢った当初にも警戒心が薄いなぁと思ったけれど、それでもこんなにもくるくると表情が変わる子だとは思わなかったから。そう考えると、今はすっかり心を許してくれているんだなと……さらに実感する。
〝お仕事以外で女の子に触れない〟と——知り合って間もない彼女にバレてしまったときも。何度目かの『自分とだけにしてほしい』なんて撮影相手に言われて……つい、弱ってしまったときも。彼女が何気なくくれた言葉が、未だに心の中心に――残っている。
『そんなに疎まれるお仕事なのかなぁ、この仕事って……。久遠ちゃんはさ、どう思う?』
『千弘さんは、とても誠実にお仕事されてます。私はそれを見て、感銘を受けたんですよ。私は、千弘さんの味方です……!』
知らず知らずのうちに警戒を緩めてしまったのも、今思えば久遠ちゃんが一緒だったからなんだろうと理解できる。何を言わなくても、穿った見方をせずにただ受け止めて、自分なりに咀嚼をして。その上で何かをくれるわけではなくて、ただ態度で信頼を返してくれるだけ……というのは。案外、心地がいいモノなのだと初めて理解した。勝手な理想を押し付けた〝|俺《﹅》〟ではなく、ただまっすぐに〝高嶺千弘〟を見て受け止めてくれたのが。彼女で良かったと、今ではしみじみ思う。
――ゼロがイチになっただけ、かもしれなくても。誇りと熱意を持って打ち込んできたこの仕事のことを、同業者にも理解されず。そんなときに現れた、なんにもこの業界のことを知らない《《ただの女の子》》が、短い期間だけでも俺を見て……この仕事に触れて、《《はじめての理解者》》になってくれたこと。それが、長らくこの仕事を続けてきた俺にとっての《《救い》》だった。
理解してくれただけじゃなくて、心から信用して……その信頼に触れて嬉しいと感じさせてくれたのも。好意を伝えて『ごめんね』と謝った俺に、間髪入れず『どうして謝るんですか』と困った顔をしてくれたことも。〝この仕事をしている限り独りきり〟なんだろうという《《割り切らなくちゃいけない》》と感じ始めていた想いごと、そんなことないと受け止めて。傍にいてくれたことに、俺がどれだけ救われたか――きっと何度話しても。あのときの満たされていく感覚も、独りじゃないという喜びも、心に灯がともるような温かさも……伝えきれはしないから。こうして今も傍にいて、そして〝《《これからもずっと》》〟を誓ってくれること。俺が唯一、本当の意味で自分を晒して安らげる場所でいてくれることが……ただただ、本当に幸福で。
……そんなことを考えながら、しばらく黙って百面相をしている様子を眺めたままでいたせいか、はたと我に返ったらしい彼女がこちらを振り向く。
「……って、そうじゃなくて……ですね!千弘さんが見てた写真のことですっ……!」
「そうだったね。ほら、これ」
おいでと手招きをすると、久遠ちゃんは大人しくソファの背面側からこちら側へと回ってくる。ぽすんと隣に腰を下ろすと、何の疑いもなく顔を寄せてくる――その素直さが底抜けに眩しくて。つい悪戯心に火がついて、寄せられた頬に自分の頬を触れさせた。
彼女の側からすれば、完全に不意打ちだったのだろう。思わずといった風にちいさく身体を跳ねさせた次の瞬間には、触れた頬が熱くなっていくのが感じられる。ふふっと漏れた笑い声に、もう……と困ったような笑みを孕んだ声がして、また元通り——頬が触れる位置に、収まった。拒絶しないで、受け入れて。柔らかに包み込んでくれるその愛情を、日常の何気ない瞬間ですら、彼女はそうして返してくれる。
――ようやく画面に表示していた写真に目をやったのか、久遠ちゃんの方からもちいさく、やさしい笑みが漏れる。
「やっぱり猫ちゃんは可愛いですね……♡」
……元来、動物が好きなのだろう。彼女は以前、何の因果か俺に耳と尻尾が生えてしまったときにも、目をキラキラさせてはしゃいでいた。写真の中の彼女も、記憶の中の彼女も、今隣にいる彼女も……いつもそうだ。子どもみたいに純真に、無垢に。その目をキラキラと輝かせている。破顔して緩んだ表情からも、やさしさが伝わってくるくらいに、柔らかな表情で。
「猫ちゃんも可愛いけど、久遠ちゃんもすっごく可愛いよ?」
「……んん、千弘さんが撮るのがお上手だからですよ……!あとは猫ちゃん効果です……!」
「そこまで言うなら、そういうことにしておこっか♡」
あまり|揶揄《からか》いすぎるのも、また困った顔をさせてしまうかなと。くすくすと笑って、その話題を切り上げた。彼女はほっとしたように息を吐くと、薄く頷く。
「それにしても、本当に猫ちゃんもやさしい顔してるね。……これとかほら、すっかり久遠ちゃんに甘えきってるよ♡」
「猫好きとしては嬉しい限りなんですけど……!うう、私の顔もゆるみすぎで……っ!」
あとで見返すと恥ずかしいです、と首を左右に振る彼女を見て、またついつい笑う。甘えてゴロゴロと喉を鳴らした猫ちゃんが、頭を押し付けるようにすりすりと彼女の手に甘えていた様を思い出す。彼女といると癒されて、ついつい甘えてしまいたくなるから……はじめて会ったはずの猫ちゃんが、すぐに心を開いたのもよくわかる。
「ふふ♡ でもちょっとだけ、俺も猫ちゃんになりたい気持ちわかるなぁ」
「え、そう……ですか?」
「うん、ほら。俺はどう頑張っても久遠ちゃんに抱っこされる側にはなれないから、ちょっと経験してみたいなとは思うよ♡」
そう返事をすれば、一度驚いたように目を瞬いたあと、彼女はゆっくりと満面の笑みを浮かべた。
「ふふ、千弘さんなら猫ちゃんになっても可愛いんでしょうね……♡」
「久遠ちゃんも結構ノリ気だ♡ その時は思う存分抱っこしてね?」
――そんな話を、何気なく交わしたのだった。
◇ ◆ ◇
「みゃおん」
昼下がりの陽気に負けてうたた寝をしてしまっていたのか、目が覚めて違和感を覚えて……ふわふわの体毛に包まれたちいさな手――もとい、前足を眺めて声を上げる。もちろん、その声も案の定……|この姿《ネコ》にふさわしいものになっていた。
一度尻尾と耳が生えた経験からか、目覚めて何故か自身が猫になっていても、思ったより冷静でいられている気がする。……まぁ、元々お仕事の都合で色んな〝あり得ない〟設定をこなしてきたせいもあるとは思うのだけど。そんなこともあるか、というのが最初の感想で、いつもの自分の視界と違いすぎる視界を案外楽しんですらいる。
どうやら俺は今、長毛種の猫になっているらしい。以前と同様、ぱたぱたと寝息を立てる彼女の腕や足に、尻尾で触れた。そのふわふわでもふもふの手触りに、久遠ちゃんはちいさく唸り声を上げて身動ぎをする。
「……ん、んん……ちひろ、さん……?」
もぞりと身体を起こした彼女が、眠そうな目を擦りながら俺の名を呼ぶ。応じるように喉を鳴らして、すりすりと腕に甘えるようにして顔を押し付けた。くすぐったさからか、ふふっとちいさく笑い声を漏らした後で「あれ?」と我に返った久遠ちゃんの声が聞こえて。まだ眠たげな色をたたえた瞳が、徐々に俺の顔を見据えて……焦点を結んでいく。
「千弘さん、えっ……ね、猫ちゃんになってますけど……!?」
驚きの声を上げ、ぱくぱくと口を開閉しながら必死に現状を理解しようとしているらしい彼女を落ち着けるように、するりと身体を寄せる。なるほど、猫の身体は流動体のようだと思うことも多いけど……本当に、思った以上にするすると動く。視線を合わせることや見下ろすことはあっても、完全に彼女を見上げることは少ない。ぺたんと普通に座るだけで、自然と見上げる形になるのがなんだか新鮮で、それだけで楽しくなった。
触れていいのか迷うようにして、先ほどからふらふらと手を彷徨わせては我に返ったように引っ込めてを繰り返す彼女に、思わず笑みが漏れる。人間だったら笑っていただろうところが、ぐるぐると楽しげに喉が鳴った。あのときも、ぱたぱたと感情に合わせて揺れる尻尾を目で追っては、じっと熱のこもった表情でひたすら見られたのだ。あまりの様子に「触っていいよ」と言った途端、本当ですかと目を輝かせていたのも記憶に新しい。
……言葉が発せない代わりに、安心して触っていいのだと意思表示も兼ねて、自ら飛び込むように、久遠ちゃんの腕の中に身体を預けて。そう言えば、いつもは俺が抱き留める側で――彼女にこんな風に飛びつくのも、はじめてかもしれない。自分からすり寄って抱擁を求めること自体は毎日のようにあるけれど、やっぱり体格差がある以上は全力で抱きつくことはできないから。
「わ……っ!」
驚きながらも伸ばされた腕が、やさしく身体を抱き留めてくれる。あたたかな温度が伝わって、自然と表情が緩む。猫の姿のときはいったいどんな表情になっているのか、想像がつかなくてほんの少しの戸惑いもあるけれど。彼女の温もりに包まれて、嗅ぎ慣れた匂いに鼻を埋めるように肌に触れた。先ほどからずっとごろごろ鳴りっぱなしの喉の音に、いかに自分が彼女の前だと気を許しているのか、いつも以上に客観視させられるようで面映い。
「ふふっ、千弘さんくすぐったいです……」
触れた肌がくすぐったいのか、身を捩りながらそう言って笑う彼女の表情に忌避感は見られない。唯一安心できる居場所……安らげる場所を得た俺の、これまで自分の中にはなかった〝我欲〟を喜んで受け入れてくれる久遠ちゃんは、最初からしっかりしているのにどこか抜けていて。こういった不思議な事態にも、最初は面食らいこそすれど《《俺であること》》それ自体には疑問を抱かずに、素直にただ受け止めてくれる。
そういう、ただ《《受け止めてくれる》》ことが心地良い。普段は過度に何かを求めたりしないのに、俺に愛されているときだけ素直に応じるどころか――求めてくれるようになったことも含めて……全部。その全部が愛おしい。離さずに抱きしめていてくれるこの腕があるから、俺はこれまで以上に仕事にも打ち込めるのだから。
「ぅにゃあ」
言葉は全部鳴き声になってしまうけれど、それでも確かに彼女に伝わっているのだろうというのは感じられる。聞き慣れた心音も、触れる温度も……いつも通り、たった一度で手放したくなくなってしまった彼女のそれだ。いつもは俺が包んであげる側の温度と体躯に、やさしく包まれてこんなに心地良くて落ち着くものなのかと、染み込んでいくように馴染んでいく温かさに身体を緩めた。
いつもは腕の中で感じているすこし高めの体温が、全身を包んでふわふわと気分を高揚させていく。道理で彼女の腕の中で、猫ちゃんたちがあんなにも甘えていたわけだと納得してしまうほど——居心地が良い。彼女の体臭と混ざった揃いのシャンプーやボディーソープの薄くなった香りが、鼻腔をくすぐる。人より優れた嗅覚に引きずられているのか、普段だったらこの時間にはあまり感じられないはずの微かな匂いすらも拾えることに、驚きつつも薄く笑う。聴力も同じで、人より良いそれが……普段は耳を澄ますか、肌を寄せて感じることの多い彼女の刻む心音やわずかな吐息を拾ってはぴくぴくと耳が反応しているのが感じられる。
ただこうして膝の上で抱きかかえられているだけで、とろとろと思考が蕩けていってしまうような――それほどに安堵してしまう。普段、惰眠を貪ったりはしない|性質《タチ》なのだけれど、こうしているだけで徐々に眠りの淵に誘われていく。
ただでさえ春めいてきたお休みの日の昼下がりの日差しなんてものは、抗いがたいほどの誘惑だというのに。一定のリズムを刻む拍動と温もりで、急速に思考がぐずぐずになっていく。それは久遠ちゃんも同じらしい。ふわぁと眠たそうな声が聞こえたかと思ったら、うとうとと瞼が落ちかけている様子だった。そのまま、膝の上に抱きかかえていた俺の身体を掬いあげるようにして、睡魔に負けて彼女はそのままベッドに身体を横たえた。抱え上げた俺ごと横になると、ぽやぽやと眠たげな瞳のまま甘えるように身体へ鼻先を擦り寄せる。
……この家にベッドは一台しかない。彼女がこの家で暮らし始めてからずっと——、俺たちは寝食を共にしている。隣にその体温があることが常で、生活の一部として溶け込んでしまった。だから、お互いにもう……その温度がないと物足りない。何かが欠けてしまったようで、心の底から安心して眠れない。
――少なくとも、俺はそうだ。仕事でどうしても家を空けてしまうことも、あるけれど……。いつも足りない。安心しきった寝顔を無防備に晒して、腕の中ですやすやと寝息を立てる彼女がいてようやく。……ないしは。拒絶も不快も一ミリもない、俺を受け入れることを《《当然》》としてくれる彼女のとろとろにほどけた声音を傍で聞きながら、体温を感じてようやく。ああ一番ここが安心する、と。実感できるから……俺も同じように無警戒で寝顔を晒せるのだ。
眠たげな久遠ちゃんから出た何気ないたった一つのその行動で、ああ彼女も同じなのだと思うだけで……こんなにも充足感に包まれる。
そう思ったら俺の意識も、もう保てそうになかった。どんどんと、微睡みに落ちて行ってしまう。すべての思考を手放してしまうまでに、そう……時間はかからなかった。
◇ ◆ ◇
太陽が傾いたせいか、些か低くなった室温にわずかばかりの肌寒さを覚える。それにつられるようにして、一気に思考が覚醒していく。ゆるゆると水中を登っていくような浮上感を感じながら、存外しゃっきりとした思考で目を開いた。
ぱちぱちと、数度目を瞬く。もぞりと身動ぎをして、元の姿に戻っていることに気付いて……思わずくすりと笑みを溢す。白昼夢のような出来事だったな、と自分でも思う。揃って不思議な夢を見ていたのだと言われた方が、納得がいきそうな不可思議な出来事。夢だったとしても、彼女が同じ夢を見て……思考を共有してくれていたのだとしたら、それでもいいと。そう思ってしまうほど、かけがえのない唯一無二の存在になっている恋人の姿を視界に入れて、俺はもう一度笑った。
「ふふっ」
今度は、思わず声も漏れてしまった。その音に、眠っていた彼女の瞼が、ぴくりと反応を示す。恐らくちいさな猫の手を掴んだまま寝ていたのであろう彼女の手は、俺の指を数本握りしめたままになっている。彼女の身動ぎに合わせてゆるく力の込められる手に、くすぐったい気持ちになる。
――きっと、放っておいてももうすぐ覚醒するであろう彼女の意識を浮上させるように。乱れた前髪の隙間から覗く額へ、唇を寄せた。
「……久遠ちゃん、起きて」
もうすっかり日も陰っている。これ以上遅くまで寝ていたら、今夜の就寝時間に影響が出かねない。残念ながら明日は仕事の予定で、いつまでもゆっくり過ごすことも難しかった。
「……んー、んぅ……?」
ぼんやりと意識はあるらしい。呼びかけに、言葉にならない言葉が返ってきた。きゅ、と甘えるように握った手に力が込められて……それから、もぞもぞと起き出した彼女の瞼がゆるく持ち上げられる。まだ夢見心地で覚醒しきっていない彼女の見せる、そのふにゃふにゃとした表情が。警戒などひとつもない寝顔の次に、本当に俺のことを心の底から信頼してくれているんだなと実感できるから――……。この寝起きのやり取りをするのが、俺は好きだ。
「ほーら、起きて。ちょっとお昼寝しすぎちゃったね、もう日落ちちゃってるんだよね」
そう言いながら、触れるだけの口付けを何度か落とす。んー、とちいさく溢した彼女が黙ってそれを受け入れて、徐々に覚醒していく瞳を間近で覗き込んだ。
「もう夜だけど、おはよう……久遠ちゃん♡」
「……おはよう、ございます……!あれ、千弘さん戻ってる……?」
さっと頬を染めながらそう挨拶してきた彼女の「夢だったのかな……」の言葉にくつくつと笑いながら、手を引いて身体を起こして。
「どうだろうね?」
俺は――わざと悪戯っぽく、片目を瞑ってみせた。この後、すっかり飢えてしまった想いを今日も、彼女に強請ることを……ひそかに心に決めながら。
目次へ戻る
2022年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
猫の日
2022/02/22
「ふふ……、やっぱりこうしてるの好きだなぁ~♡」
少し遅い昼食を終えて、のんびりと過ごす昼下がり。最初は隣あって座っていたはずが、いつの間にか抱きこまれるようにして眼前に迫った柔和な顔立ちに耐え切れず、ほんの少し視線を逸らす。
すりすりと寄せた頬を撫でながら、そう言う千弘さんは楽しそうだ。お付き合いし始めてからしばらく経つものの、私の方は千弘さんのスキンシップの多さに、一向に慣れそうにない。
気恥ずかしさから、撫でられている頬が熱くなるのを感じる。恐らくもう顔は真っ赤だろう。案の定――そう時間の経たないうちに、笑いを含んだ千弘さんの声が降ってきた。
「久遠ちゃん、顔真っ赤だよ?すっかりりんごほっぺちゃんだね♡」
「……う、うぅ……千弘さん〰〰っ」
「ごめんごめん、可愛すぎるからついからかっちゃった……♡」
最近特に反応を楽しんでいる気のある千弘さんに、抗議の視線を送るとにこにこと笑顔でそう謝られる。悪びれた様子が一切ないのに、毒気の一切ない笑顔でそう言われてしまうとつい許してしまうのだ。むぅともう一度だけ抗議の意味を込めて頬を膨らまして視線をやったものの、彼は変わらずに笑顔を浮かべている。
「やっぱり千弘さん、なんだか猫ちゃんみたいですよね……」
むにむにと頬を突いたりやさしく揉むように抓っては満足げな彼のされるがままになりながら、思わずそう溢す。
ぱちくりと目を瞬いた千弘さんが、少しだけ考える様子を浮かべて「うーん」と声を上げた。
「俺……猫みたいって言われたの、はじめてかも?」
「えっ、ほんとですか?」
「うん、ほら俺サインでも描くのうさぎちゃんだし……そういうイメージは結構大きいからね」
そう言われてなるほど、と同意する。千弘さんが|AV男優《チヒロ》として活動している際に使用しているサインには、確かに可愛らしいうさぎが添えられているのが常だ。
あとはもう、代名詞になっている桃とセットで〝チヒロ〟のサインは書かれている。桃は元々千弘さんが好きなものだし、うさぎもわからなくはないのだけど——わかるのだけど、理由を聞かれるのが嫌なので千弘さんの前では触れずにいる――髪色から|イメージカラー《ピンク色》と言い、連想するものすべてが同じ色と言うのもなかなかに珍しい。
ふむふむと頷いていると、千弘さんがずいと顔を寄せた。
「……で、どうして久遠ちゃんは猫みたいって思ったの?」
鼻先が触れ合うほど近くで、まっすぐに瞳を覗き込まれてそう尋ねられて。……誤魔化せる人がいるだろうか、と。ときどき思う。
「……甘えん坊な猫って、抱っこも大好きですし……その、ずっと近くにいたり、すり寄ってきたりするじゃないですか」
先ほどまでほとんど抱っこされるような体勢だったのだ。千弘さんはその長身もあって《《抱っこされる側》》にはならないけれど。とにかく、お家の中だと常に触れていることが多い。いつぞや本人が言っていたように〝愛しいと思ったらキスをする〟という日を仮に作ったとしたら、一日中本当にずっとキスしていそうなほどに、である。
「賢いし、あざといというかズルいというか……猫ちゃん見てると、自分の可愛さをわかっているな~って思うことありません?」
ああいう感覚です、と言うと彼は堪えきれずにちいさく噴き出した。
「教えてくれてありがとね♡ 久遠ちゃんは俺にしてやられてばっかりだもんねぇ……♡」
その上、俺のお願いに弱いし……とくすくすと笑った千弘さんの長い指が、そっと唇に触れる。指先が触れるか触れないかの位置で、そっと唇をなぞられて。
――ただ、それだけのことで。じわり、と耳までさらに熱くなっていく。
「ほーら、今も意識しちゃってるでしょ?」
全部かーわいい表情に出ちゃってるよと言われて、言い返せずにぐ……と言葉に詰まる。唇の上を何往復かした指先が、ぴたりと動きを止めて。――その瞬間、思わず吐息がこぼれ落ちた。
自分の鼻先に当たった呼気の熱さに、また顔が朱に染まっていく感覚がする。恥ずかしいと思う気持ちはあるのに、それよりも喜びが勝る……なんて。千弘さん以外では、考えられもしない。
「久遠ちゃんも十分猫っぽいけどね♡」
もう期待しちゃってる瞳してる、と言うと笑って「大人しい性格の猫ちゃんって、甘やかされるとそのまま力抜いてされるがまま~って子も多いもんね♡」と続けた彼の言葉に、その通りかもしれない……なんて考えている時点で。多分、私はずっとこの人に負けている。
「……すっかりダメになっちゃったね?」
「千弘さんが、したんですよ……」
そう返事をしてようやく、重ねられた唇の感触に……また。燻るような熱が、煽られて火が付く感覚が――した。
目次へ戻る
2022年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
薫染
2022/01/30
「……それじゃ、お仕事行ってくるね♡」
「はぁい……行ってらっしゃい、千弘さん♡」
玄関先で手を振り合って、お仕事に行く千弘さんの後ろ姿を見送って。エレベーターホールに向かう途中、軽い会釈をしてくれた岡持さんに会釈を返す。
その後ろを着いていく千弘さんが、お茶目にウインクを飛ばすと、もう一度手を振って去って行く。
それに慌てて小さく手を振り返し、後ろ姿が見えなくなるまで見送ってから、部屋のドアを閉めた。
◇ ◆ ◇
……鍵を閉めて、ひと息つくと部屋の中へ戻る。よしっと気合を入れると、寝室へと向かう。
千弘さんは大層にマメな人なので、朝からお仕事の日でも、朝食後の片付けどころか、お掃除まで大体終わらせてからお仕事に向かう。
さすがに、細かなお掃除は家にいる私がすることが多いけれど。それでも家のほとんどのことを、千弘さんがしていると言っても過言ではない。
すごい人だなぁと改めて思う。千弘さんは謙遜してのことなのか、感心してつい言葉を溢しても、そんなことないよと笑ってくれるけれど。
「……うーん、だって今日私がすること……お布団干すくらいしか残ってない……」
こればかりは干しっぱなしにするわけにいかないこともあって、すっかり私の仕事になっている。
「よいしょ……っと」
先に拭いておいたベランダにお布団を運んで、枕も陰干しをして。布団乾燥機を使うより、どうしても気分的にお日様に干した後のお布団の方が好きなんだなぁと少しだけ言い訳をした。
文明の利器に頼りたくないわけではないのだけど、どうしても気分が上がる気がするのは、圧倒的にお日様の匂いなのだ。
そんなちいさな我が儘も、千弘さんは「わかるよ、気分上がるよねぇ♡」と受け入れてくれるので、ついつい甘えてしまう。
これでいいのかなぁと、ときどき不安に思うことはある。千弘さんはお家にいて、待ってくれているのが一番だよって言ってはくれるけれど。
……僅かな期間、臨時マネージャーとして働かせてもらっていたとはいえ、今の私は完全に無職で千弘さんのお家にご厄介になっている状態だ。
「……さすがに、千弘さんに甘えすぎな気がするんだけどなぁ」
千弘さんにいいから、と言われてしまうと強く言い返せない。せめてもう少し力になりたいと思うのに、無力だなぁと思い知る。
「俺がお仕事を終えて帰ってきて、久遠ちゃんに癒されたいんだからいいの♡ ……ね?」
言われた当時は意味もよくわからないまま了承したような気がするが、さすがにこの言葉の意味も、今ならわかるようになった。恥ずかしくはあるけど、千弘さんがそう求めるのなら、応えたいというのが私の答えだ。
……と、言うよりも。まあ、その。毎日のようにそういうことをしていたら、するのが当たり前のようになっている、というか。いやでも意識してしまう、というか。特にその、月のものでしばらくご無沙汰になったあとなんかは、こう。つい、そういう気持ちになってしまいがち、というか。
もごもごと口の中で言い訳をすると、そういう意味でも色んな変化があったなぁ、と思いを馳せる。
……職を失い、企業面接を装った裏ビデオの撮影に引っかかりかけ、女優さんと間違われて、お詫びということで臨時マネージャーとして雇ってもらい、そのまま千弘さんとお付き合いすることになって、同棲して……と。
――ここ数ヶ月の間の出来事のはずだけど、改めて振り返ってみると、その濃さに思わず瞠目しそうになる。
というより、他人に話したところで到底信じてもらえないような出来事が並んでいるなぁ……としみじみ実感した。
「これ全部、この一年の間の出来事なんだよね……」
思わず照れが込み上げてきて、ふるふると首を左右に振ってそれを追い払う。
色々と思い出してしまって、頬が熱い。気分を切り替えようとキッチンへ向かう。冷蔵庫の中身を確認して、買い足す食材を決めながら飲み物の補充をすることにした。
千弘さんは常に複数種類の飲み物をストックしているのだけれど、初めてそれを知ったときはあまりのマメさに驚嘆したものだ。私自身、何が飲みたいかと問われて答えればおおよそ出てくる、その種類の多さに、すべてを把握できていない。
というよりほとんど千弘さんがやってくれるおかげで、よく使うもの以外は未だにあまり場所を把握してない、という方が正しい。
気付けば食器棚の配置も〝私の手の届く範囲〟にお茶碗なんかは移動されていて、この暮らしを始めたばかりの頃に使わせてもらっていた客用茶碗なんかは、いつの間にか棚の上方に収められていた。
これでも私は、どちらかと言えば身長は高い方で、日常生活で困ったことなどなかった。そのせいか、こういう部分で気を遣われるのは初めてで、なんだか妙にくすぐったい。
〝ちいさくて可愛い〞などと言われたのは、千弘さん相手が初めてで。もともと千弘さんひとりで暮らしていた部屋なのだから当然と言えば当然なのだが、総じて高めに設えてある部屋というのも、なかなかに新鮮だった。
そんなことを考えながら、ストックを取り出そうと戸棚に手を伸ばす。ほんの少しだけ背伸びをして、指先で目当ての茶葉の入った缶を引いたところで――するん、と手が滑った。
「あ」
受け止めようと、慌てて手を伸ばす。やや大きめの缶を手で受け止め損ね、ついで身体を寄せてなんとかキャッチした。ぽふんと、缶がぶつかる鈍い衝撃が身体に伝わる。
「……っ、ふ」
思わず漏れた声に、反射的に片手で口を覆って。誰もいない、聞いていないことなど明らかなのに、バツの悪さから思わず周囲を見回した。当然、部屋の主はいない。先ほどその背中を見送ったのだから、間違いようがない……のに。
誰にも聞かれていないことに心底安堵して、ほっと息を吐いた。
――じわり、と。身体の奥底に染み出すような淡い感覚が、する。ぶんぶんぶんと。音がするほど大きく首を振って、雑念を追い払う。急に頭を激しく振ったせいか、若干耳が熱い気がするけど、それは無視して。
「……ささっと新しいの作って、買い出しに行こう……」
深く息を吐いて、そう溢した。
◇ ◆ ◇
出かける前に布団をひっくり返して、食材の買い出しを終え。帰宅後に布団と洗濯物を取り込み、ベッドメイクをする。
「ふふっ、今日もお布団も洗濯物もふっかふか……!」
日常のささやかな幸せになりつつある、この手触りと匂いに勝手に頬がゆるんでいく。
ふと時計を見上げて、割といい時間になっていることにようやく気付いた。リスケが続いた結果、今日の撮影は一本撮りになったので、もうしばらくしたら千弘さんのお仕事も終わるだろう。
――同棲を始めたとき、千弘さんから使っていない一室を自室として与えてもらったけれど。ひとり暮らしをしていた家から、家財道具をすべて持ってくるわけにもいかず。結局最初に運んできた荷物の他には、幾許かの荷物を運び込んだだけで、かつての〝私の家〞は早々に解約してしまった。
ひとりの時も結局ほとんどこうして共有スペースで過ごすことがほとんどで、あまり自室に籠ることはない。……本当に。ただ、傍にいることがこんなにも居心地が良いだなんて、たった数ヶ月前まで知らなかったのが嘘のように。
そこにいるのが、この先もずっと当たり前であればいいのに……と、強く思う。――隣で、肌で、触れあって感じる、体温も心音も。あんなにも誰かの隣にいて、〝安心する〟という感覚を覚えたのは初めてで。普段、隙間を埋めるかのように引っ付いているせいだろうか。たったの数時間。それすらも離れているのが惜しい、などと。
「……我が儘で、迷惑な感情だなぁ……」
呻くように言葉をこぼして、ぽすっと頭をベッドに預けた。
求められた分、応えたいだとか。色々とそれっぽい言葉で誤魔化してはいるけれど、要は普段あまり我が儘を言わない千弘さんに私の前でくらい、我が儘を言ってほしいし欲張りになって欲しいのだ。これだって、ただの私のエゴかもしれない。
こんな我が儘を〝優しいだけ〟だと言ってくれた。自惚れるならば……、他の人の前ではそんな風に控えめな彼の、〝我欲〟を向けてもらえていることに。許されるなら、自分の前でくらい遠慮も手加減も、気遣いも不要でありのままの〝千弘さん〟としていられる存在であれればいいと。そればかり、繰り返し思う。
「う〰〰〰ん……」
本人不在の場所で、こんな風に考えていても埒が明かないことなど知っているはずなのに。ひとりになると定期的に、こうして唸っているのだから不毛だなぁと自嘲した。
ヴーッと、くぐもった音が聞こえて反射的に顔を上げる。ベッドに凭れかかっているうちに、うとうと微睡んでしまったらしい。
そういえば携帯をテーブルの上に置きっぱなしにしていた、と思い出して慌てて駆ける。通知を開いて、メッセージの内容に目を通す。
『お仕事終わったよー♡ 事務所で軽い打ち合わせしてから帰るね~♡』
その内容に了承の返答を送って、ひとつ伸びをすると気持ちを切り替えた。
◇ ◆ ◇
ガチャンと鍵の開く音がして、弾かれたように顔を上げる。
「ただいま、久遠ちゃん♡ ちょっと遅くなっちゃった、待たせてごめんね?」
「……おかえりなさい、千弘さん♡ お仕事ですもん、気にしてないですよ!」
事務所で行う打ち合わせの時は、千弘さんが本当に信頼している事務所の方々ばかりになるからか、長引きがちなのを知っている。私自身、事務所の方々には短い期間とはいえお世話になったし、顔を知っている方も多いので、千弘さんが〝気を張らなくていい時間〟なのであればそれが長くなるのは寧ろいいことだと思っているのだけれど。
「……んー。じゃあ久遠ちゃんはひとりで寂しくなかったの?」
ほんの少しだけ。意地悪な表情を浮かべて問いかけながら、千弘さんが手を伸ばす。その腕の中に収まりながら、くすりと笑みを漏らした。
「寂しいのは……寂しかった、ですけど」
「ふふっ、でしょ……?俺もそうだから、ぎゅーってさせてね……♡」
こくりと頷いて胸元に顔を寄せると、ぎゅうと身体に回された腕に力が込められた。服から少しだけ覗く、見慣れたタトゥーがいつも通りの視界にあることになぜかひどく安堵する。
ふたりともいい大人だと言うのに、どうしてこうも際限がなくなってしまうんだろう。
これが本当に〝人を好きになる〟と言うことなんだとしたら、どうしようもなくしあわせなのに、どうしようもなく不安になるのも、仕方のないことのように思える。相手が自分のことを見てくれていることも知っていて。自分だって、相手以外の人のことなど目に入りもしないのに。もっと、まだもっと……と。どこまでも欲しくなってしまう。
千弘さんのお仕事のことを、嫌だと思ったことはないのに。縛りたくないと語ってくれた言葉に呼応するように、ありのままの気持ちを伝えられなかったこともあったけれど。
きっと、今。すこしだけ、互いに〝変わったな〟と感じる関係性を考えた上で。他でもない千弘さんが〝俺だけを見て〟と言ってくれるということは、私も……そう、求めても許されると。思ってもいいだろうか。
ずっと、好きであることに変わりはないけど、以前よりも愛しい……可愛い人だなぁと思うことが増えた。一歩感情から身を引いて、どこか諦観が見え隠れしていた千弘さんが〝以前より活き活きしている〟と。ずっと魅力的になった、と評価されることがうれしくて。
――すり、と鼻先を埋めるように強く抱き着く。同じはずのシャンプーとボディソープの香りが、千弘さんが纏うと全然違う匂いになる。この匂いと体温に包まれている瞬間が、途方もなく幸福で。どうしようもなく嬉しくて。手放したくないと、どんどん我欲が強くなっていく。
「どうしたの、久遠ちゃん?……なんだか今日は甘えん坊だねぇ♡」
「……だって寂しかった……ん、です……っ」
「……そっか♡ ぎゅ~ってしてもまだ足りないなら、ねぇ?お顔上げて」
言われるがままに、顔を上げる。真正面からかち合った視線に、燻っていた熱が煽られる感覚がした。
すり、と唇を撫でられて反射的に薄く開く。くす、と微かに笑う吐息だけが降ってきたのを耳で感じた次の瞬間には、唇を食まれていた。
甘噛みされて、ぴりと電流が身体を駆け抜けていく。ふと力の弛んだ肢体を抱え直すようにされて、逃げ場がなくなる。優しいのに、拒否権など与えられずに差し込まれた舌に自分のそれを絡めて。どちらから洩れている吐息なのか、鼻先で息が混じっていく。同時に湿度を変えた声が、鼓膜を震わせる。
「ふふっ、久遠ちゃんすごい勢い……♡」
ぺろりと唇を舐めあげ、明らかに熱のこもった視線でそう囁かれて、カッと顔に熱が集中していくのを感じた。
「また、真っ赤になっちゃったね♡ ……ほんとに可愛いんだから」
――これだけで照れちゃうのに、俺のこと待ち侘びてそんな顔しちゃうんだもん、と。
耳元で吐息混じりに囁かれ、ぴくりと肩が震える。反射的にぎゅう、と目を瞑った間に膝裏に手を入れられ、易々と抱え上げられて。気付けばいつもの通り、お姫様抱っこをされていた。
「……わっ、千弘さん……!」
危ないですよ、と言おうとした口をそのまま噤んで、代わりに首に手を回す。
「そうそう、大人しく掴まっててね♡」
今日はシャワーは後回しでいいか、と呟かれた言葉に返事の代わりに手に込めた力をすこし強めて。微かに、伝わるかどうか程度の首肯を返す。
変わっていく自分に、戸惑いがまったくないわけじゃない。……でも、千弘さんと一緒にいての変化なら、それでいいと思えるから。
……想いを伝えるたび、言葉で伝えきれない感情を態度にして交わすたび。うち震えるほどに、満たされるこの形容しがたい想いごと。全部、伝わればいいのにと何度も思う。
そうして、出来ればこの先も――あなたのその、心の機微ごとぜんぶ。余さず、隠さずに……私にぜんぶをくれますように。
独占欲などという、やさしい言葉で片付けられない気さえするほど、溢れて溢れて仕方のない感情を……言葉にするのは気が引けて。
「俺も全部あげるから……、久遠ちゃんも隠さずにちゃぁんと俺に全部ちょーだい♡ ……約束、したもんね?」
「は、い……、千弘さん……♡」
震える声で返事をして、やさしい振動を感じながらその肩口に顔を埋めた。
目次へ戻る
2021年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
空白
2021/11/29
「……演習は以上!先の経験を次に活かすように」
突き抜けるような青い空の下、土煙が上がるなか――、よく通る声の、号令が聞こえる。
執務室の窓の桟に腰掛け、その様子を一瞥した。ざ、と音を立てて敬礼をする隊列の前に、小柄な姿が見える。背中を伸ばし凛と立つ姿は可憐ささえあるのに、そこから漂う緊張感に、例え同階級の者であろうが、身じろぎすら出来なくなるのだ。
――僅かに静寂が訪れて、風が窓を打つカタカタという小さな音だけが部屋に響いた。
「……総員、解散!」
一拍の間を置いてそう短く号令をかけた准尉の声に、隊員たちは最敬礼をやめて宿舎の方へ駆けて行く。走っていく彼らの姿を見送ったあと、不意に彼女は空を見上げた。
今回彼女の進言で行われた演習は、野営訓練と遠征先……慣れない場所かつ戦闘に向かない場所での夜戦を想定してのものだった。俺たちと別の師団ではあるが、そこに所属する隊が遠征中に敵陣営とかち合い、そのまま戦闘となり軽被害を受けたことも関係するのだろう。
准尉が所属・指揮官を務める第三部隊も、ここしばらくで下士官の補充と士官クラスの要員交代もあり、そろそろ大規模な演習をする必要があると語っていたことを思い出す。
それにしてもと、つられるように視線を空へと移動させて、ほとんど丸一日前に出立した彼女らのことを思って、薄く苦笑をした。この照りつけるような日差しでは、ほとんど寝ていない身体には酷だろう。
隊員らの多くは、この後は夕方頃まで余暇を言い渡されているはずだが、指揮官かつ隊長でもある准尉は、この後も任務が続く。佐官相手に報告を行う軍議もあって、まだ休むわけにはいかないのだ。多少なり負傷者は出たはずで、その把握・報告も必要になる。
ただでさえ軍人の多くは男だ。そもそも身体のつくり、基礎体力からして違う彼らを率いて前線で戦い続ける過酷さは相当なもののはずなのに。本当に強い子だな、と改めて思う。
軍帽をかぶり直した彼女が視線を下げる。ふとこちらを見ていることに気が付いて、ひらひらと手を振った。
気が付いたのか、一瞬間をおいて彼女が頭を下げる。ここでの俺と彼女の関係は、恋人である前に直属の上司と部下――|士官《中尉》と|准士官《准尉》だ。
天性のセンスからのものか、戦闘において彼女のあげた功績は数知れない。この基地に配属された頃から、戦闘センスはほかの誰より抜きんでていたし、戦場でも冷静に俯瞰して戦況を見られている。立案も提示も上手く、上官に対しても物怖じせずに発言する。
本当に、よく出来た部下だ。だからこそ抱えているものがたくさんあるはずなのに、そんなことを感じさせない。そんなところが愛らしくも、俺の心を苦くさせる。
頭を下げた彼女が、その場から立ち去っていく。それを見送って、俺も窓から離れた。
……ノックの音を、密かに待ち侘びながら。
◇ ◆ ◇
コンコン、と控えめな音で扉が叩かれる。どうぞと応じて、扉が開いていくのを目で追った。
「失礼します、高嶺中尉」
ただいま帰還しました、と言う声と共に、執務室の中に彼女が一歩踏み込む。
「おかえり、神里准尉。今回の演習の首尾は?」
「は。……まず先んじて配属された下士官ですが、もう少し練度を上げるために通常の訓練を少し変更した方が良いかと思います」
このままでは野営時に単独哨戒は難しいでしょうし、今回もそれで負傷者が出ていますと報告を述べる様子は、いっぺんの緩みもないほどに真剣だ。
「……そうか。負傷者は何人ほど?」
「10名少々ですね。ほとんど擦過傷や打ち身で任務に支障はありません。……が、そのほぼすべてが新たに配属になった下士官です。こちらの指揮もよくありませんでした」
「まあ、ただでさえ慣れない領地での初演習だ。その程度の人数で済んだなら僥倖だろう」
「……中尉。怪我人は守備陣営側の作戦員のみ、ですよ。敵陣営側をやってもらった隊員には詳細な指示は出していたにしろ、乱戦後は主だった指揮なしです。それでこの偏りはまず間違いなく戦場では響きます」
そもそも、と彼女は言葉を続ける。
「戦場では敵も、味方もより鬼気迫る状況です。周囲には血も、怒号も、悲鳴も飛び交います。武器訓練も兼ねているので、新兵には銃剣の使用も許可しました。対するこちらは木銃です。大きな負傷が出なかったのは確かに幸いですが、まず間違いなく今の状況では下士官たちは負傷すればそこまで――。気力が折れます」
本当に、見た目に反して冷静で、俯瞰的で。それでいて誰よりも仲間に対して情に篤い。だから、こうして准尉はあらゆる人員のことを気に掛ける。失わないように、失わせないように。
「もちろん、分かったうえでの評価だよ。確かに課題点は多いが、ひとまず皆無事であったことくらいは褒めてあげないとね。……そうじゃないと、折れる心もあるからさ」
そうでしょ、久遠ちゃんと。ふと口調を緩めてそう言えば、彼女は少し押し黙った。不服そうではあるが、俺の言ったことにも筋が通っていることを知っているから、何も言い返さない。
スイッチが入っている時の准尉は、誰よりも苛烈で、|峻烈《しゅんれつ》だ。自身はもちろん、隊の誰にも敵前で背を向けることを許さない。
――強いなぁ、と思う。彼女は怖くないのだろうか、と馬鹿なことを考えることがある。
そんなわけはないと、知っているのに。俺の腕の中でだけ見せる、年相応のあどけなさを残すあの表情のときだけ、押し隠しているのであろう複雑な感情で、その瞳を小さく揺らすのだから。
それでも、俺の前でも彼女は弱音を吐かない。ただ強く笑って、前だけを向いている。そうすれば俺が次にどうするかを、本能的に察しているからだろう。
「……はぁ、本当に。中尉の飴のおかげで成り立っているところがありますね……。お言葉の通りです。褒めるところは褒めないといけませんでした」
あとで怪我の様子を見がてら各人のところを回ってきますと言って、ようやく彼女は表情を緩めた。
「うん、そうしてあげて。……っと、でももうすぐ軍議の時間だよね。どうせ俺も出るしそれまで休んだら?この時間帯まで起きてると、つらいでしょ」
椅子を引きながらそう言えば、久遠ちゃんはほんの少しだけ眉根を寄せる。
「……もしかして、さっき空睨んでたの、見てました……?」
「あはは、うん。偶然、ね」
「……偶然、ですか。中尉が言うならそういうことにしておきます。で、先ほどの提案ですが。……乗っても?」
「ふふっ、もちろんいいよ。……どうする?お疲れだろうし、ぎゅってしてあげよっか?」
「それは、さすがに……気が抜けてこの後の軍議で使い物にならなくなったら困るので、一旦遠慮します」
「一旦、なんだ?」
「言葉の綾です……!」
からかい過ぎちゃったかと笑いながら、ほんの少し鼻白んだ彼女を手招きした。こういうとき、普段は無駄だなと思うのに、このやけに豪奢な執務机がここにあってよかったなと、雁字搦めの地位でひとつだけ、感謝をする。
そそくさと足元の机の下に潜っていった准尉が、足を抱えて丸くなる。重たげな瞼を必死に持ち上げている様子からも、どれだけ気を張っていたのかが伝わった。
彼女は准士官で、佐官以上も出席する軍議に遅れるわけにもいかず、これまでだって、いつもこうして気を張っていたのだろう。その小さな身体に不釣り合いなほどの荷物を背負い、潰れないように。
早々に机の隅に頭を預けて目を瞑ると、彼女はたちまち眠りに落ちていってしまった。お疲れ様、と唇だけでつぶやいて手を伸ばす。こうして横にすらならずに仮眠を取ることにも、すっかり慣れてしまった様子の彼女を見ていると、些か複雑な気持ちにもなる。
どう見たって、こんなに小さくて、ともすれば簡単に折れてしまいそうな体躯をしている女の子が、こんなところにいるのは向いていないだろうに。前線に出られない俺の代わりに兵を率いて、一番危険な戦線で身体を張り続ける彼女に……こんなことは言えないけれど。それでもずっとその気持ちは拭えなくて、俺は言葉の代わりに眠る彼女の頬に、指を這わせた。
――どうか、このひとときだけでも、彼女の心が真に休まりますように、と。
するりと、撫でるように頬に這わせたその指に、擦り寄るようにして眠る准尉が顔を寄せる。……こんな風に気を許してくれるのが、俺だけなんだという事実に、仄暗い充足感で身体が満たされていく。
すり、すり、と。何度も指先で、まだ少し砂っぽい彼女の肌を何度も撫でた。
◇ ◆ ◇
背後で鈍い音を立てて、執務室の扉が閉まる。その音を合図にするように、歩きながら俺はふう、と声を上げた。
「んん〜っ、今日の会議は長引いたねぇ」
「激化してきている戦線も多いですからね。……この状況下で担当任務の調整を含む提案をしたので、反対意見が出るのは想定していましたけど……」
双方の譲歩範囲を探るのにここまで時間がかかるとは、と。疲れた《《よう》》にではなく、本当に珍しく疲れ切った声でそう弱音を吐く准尉の顔には、色濃い疲労が浮かんでいる。
それもそうだろう。たかだか十数分程度の仮眠は取ったにしろ、丸一日半動きっぱなしになっているのだ。
この状況で会議の間中、疲れなど微塵も感じさせなかった彼女が、俺の前では疲労を滲ませる。
じわじわと込み上げてくる感情を感じながら、俺は椅子に腰を下ろし彼女の方へと腕を伸ばす。
「さすがにあの仮眠だけじゃあ、お疲れだよねぇ」
伸ばされた腕を見て硬直し、こちらの表情を伺っている久遠ちゃんに笑みを向けた。
「ほら、俺が癒してあげるからおいで?」
「……い、いやあの……!演習から戻って湯浴みしたとは言え、本当に浴びた程度なので……!」
ぶんぶんと音が鳴りそうなほど首を左右に振る様子に、思わず笑みが深まる。ふふ、と堪えきれずに漏れた笑い声に、彼女は顔を赤らめてむっと眉を寄せた。
「気にしないよ、そんなこと。ほーら、遠慮してないでおいで?疲れてるでしょ?」
「……食い下がっても無駄、でしょうから……行きます、けど」
色々と目を瞑っていただけると、と小声で言いながらようやく俺の腕の中に歩んできたその身体を、ぎゅっと抱き寄せる。
「本当にお疲れ様……♡」
そう囁いて頭を撫でて、顔を覗き込む。先ほどまで凛々しかった表情の面影などどこにも、一片も残っていないほど、緩んだ表情をした彼女と目が合う。
「ふふっ、すっかり表情が蕩けちゃったね……♡ こんなに蕩けた久遠ちゃんの顔、部下には見せられないね?」
最初の複雑そうな表情までも溶かしてしまうくらいに。目を細めただ撫でられるがままになっている表情に、戦場を駆け目を惹く勇猛な将の面影などどこにもない。
……ただ、俺の腕の中で脱力して抱擁と体温とを享受している姿は、その瞬間だけ彼女のことを〝准尉〟ではなく、ひとりの女の子に戻す。とろんと落ちた瞼で見上げてくるその表情に、思わず喉が鳴った。
「……そう言う千弘さんも、部下には見せられない顔ですよ……?」
そう言いながらふにゃりと笑い、久遠ちゃんはすりと頭を俺の身体の方へと寄せてくる。
その身体からはすっかり力が抜けていて、もうそれは身体を寄せたというよりしなだれかかっている、と表現した方が正しい。俺が抱き締めているからかろうじて立っているのであって、ここで力を緩めたら、すとんと床に落ちてしまうであろうほどだ。
彼女が言う通り、俺も例に漏れず中隊長として部下の前で晒す顔ではなく、ただひとりの男の顔をしているのだろう。
「じゃあ、そんなところでもお揃いだ♡」
そう囁くように言いながら、笑って顔を寄せる。至近距離で見つめた顔は、このあと俺にどうされるのかを知っているから、すでに瞳が潤んでいた。本当にそういうところがかわいいなぁと、表情筋がどんどん弛んでいく。
互いの呼気を感じるほど間近で、見つめあう。時間にすればたった数秒のことなのに、それだけで彼女の拍動が速くなったことが、触れた身体から伝わってきた。同時にじわりと上がった体温が、キミの匂いを濃くする。汚いだとか、心配しなくていいのにと思いながら、頭の片隅でこの後久遠ちゃんを説得するための言葉を幾つか考えた。
「……千弘、さん……」
張りのよく、通る声じゃない。甘さを滲ませて弛んで、かすかに震える声で、キミはそうやって俺の名を呼ぶ。昼間の、互いに部下の前で中隊長と第三部隊隊長兼中隊演習掛として呼びかける〝高嶺中尉〟という他人行儀な呼び方ではなく、〝千弘さん〟と。
俺の前でしか見せない、ひとつひとつの仕草や表情が、ぜんぶ、丸ごと愛おしくて。
名前を呼ばれて僅かに、顔を寄せる。そうすると彼女が大人しく目を瞑ることを知っていて、俺はいつもそうしてしまう。キミがキミの意志で俺を受け入れてくれているのだと、実感できることがなによりも心を打ち震わせるから。――今も、ほら。静かに目を閉じたキミのことがいじらしくて、どうしようもない。
静かにキスをする。触れて、重ねるだけのキス。それだけでもさらに表情を変えてしまう彼女のその全部を逃さないように、ただ欲張りな男としての貌を晒して、何度も。
上官にも部下の下士官たちにも、もちろん同輩たちの誰にも見せない、勇敢さとは対極の表情を晒して――、大人しく俺の腕の中に捕まって。俺の与えるものすべてを享受して、戦慄く声で、震えた喉で、吐息混じりに俺の名を呼んで。
「あは、もう蕩けきっちゃったの?そんな顔されたらもっとしてあげたくなっちゃう……♡」
そう言って、顎を指先で持ち上げる。戸惑うように一瞬視線が逸らされて、その隙をついて唇を食む。くぐもった声が漏れて、しんと静まり返った空間に零れた。
今日はもう平時の任務時間は終わっている。日中、中隊長に当番でついている人員も、もうこの部屋にはいない。中隊長室でもあるここは、俺の仕事場所兼――個室でもあるからだ。
准士官でもある彼女も、本来なら中隊事務室が割り当てられるのだろうが、部隊長と演習掛を兼任していることもあり、中隊附将校としては異例の個室を宛がわれている。本来は俺の中隊長室だって、あくまで執務室で私室とは別もののはずだった。俺だって戦線が激化するまでは普通に将校事務室で働いていたし、だから前線へも出ていた。この中隊にはもう、中隊長を務められる大尉クラスの人員が、残っていないのだ。俺たちの祖国は、それほどまでに追い込まれている。だから、かつては別の執務室だった部屋まで一緒に、俺の私室として割り当てられて――危険な任務を、死地に赴くような命を、部下に……彼女に下さなくてはならない。
これまでもそうだったし、これからもそうなのだろう。俺は何度も、口の中に広がる苦い思いを噛み締めながら、《《中尉》》として彼女に戦場へ出るよう告げねばならないのだ。表情を曇らせず、戦況を読んで、ただ《《上官命令》》として。我が師団最高の部隊となった、第三部隊部隊長である……神里准尉に。それだけで、胸を渦巻く想いが洪水のように溢れそうになる。本当はその手を縫い止めてでも、引き留めたい。けれど、それでは見逃してくれている大佐にも恩を仇で返すことになるし、何より一番肌で激化している戦火を、戦場を知る彼女に拒絶されてしまうのだろう。行かないでというたった一言がこんなにも重くて、ただその一言が紡げない。剣を振るい、あの燃え盛る戦火の中……ただ前を見据えて、その瞳に灯した揺らぐことのない炎を爆ぜさせる准尉の姿に、目を奪われたのは……俺も、例外ではないからだ。
互いに雑居部屋でないからこそ、こうして人目を忍んで会うことも叶う。普段は枷になるそれのおかげでこうしてふたりでいられるのだから、こんな時ばかりは自分の感情に素直にあろうと、そっと胎の底を焼くような恐怖を追い払った。今、この瞬間はただ、彼女のぬくもりに溺れていたい。
薄く開いた唇から舌を滑り込ませて、咥内を弄ぶ。ときおり漏れる声ごと食らうようにして、深く。――もっと深く。
ただでさえ力の抜けていた肢体から、さらに力が抜けていく。かくんと膝を折りかけた体躯を抱き留めて、ようやく解放する。
引いた糸を指で拭って彼女を見やれば、薄くなった酸素を求めて喘鳴をあげながら、肩で息をしていた。俺の胸に手を当てて、何か言いたげな表情でこちらを見上げるその顔が、さらに劣情を煽っているなんて、きっとキミは気付いていないのだろうけど。
紅潮した頬と涙目で睨めつけられたところで、嗜虐心を煽るだけだと言うことを、理解しないままのキミの方が好きだから……言ってあげない。
「ねぇ、久遠ちゃん。もっと触れたい……って言っても、怒らない?」
「……っ、だから、まともに身体も洗っていないんですが……っ」
俺が触れることが、ではなく。《《このまま》》が嫌だと声を上げるところが。情欲を掻き立てる。止まれなくさせるのに。
「いいよ、キミが気になる気持ちもわかるけど……ごめんね、一日以上ぶりにようやくキミを抱き締められたから……どうしても離したくなくて。だめかな?」
手を握り、するりと親指でその小さな手の甲を撫でる。ぴくりと小さく肩を震わせて、眉尻を下げた困惑の表情が、俺の顔を見つめた。
「……千弘さん、私がその言い方に弱いのを知っていて、言ってますよね?」
苦笑してそう言うと、彼女は指先に力を込めて俺の手を握り返す。その拙い返事を汲んで、彼女の身体を抱き抱えて隣の私室へ移動する。何度も抱き竦め、抱え上げたその身体は何度抱き上げても、小さくて軽い。剣を振るい戦場を駆ける身体は筋肉質で引き締まっているのに、俺なんかよりよほど軽いのだ。
「それでも拒絶しないでいてくれるんだから、久遠ちゃんは優しいよねぇ」
くすくすと笑みをこぼしながらそう言うと、暗がりでもわかるほど彼女の顔が赤く染まった。そうして小さな声で、「そりゃあ私だって欲しいですよ」と呟く声が聞こえる。
戦場の厳しさを、自分たちの明日の危うさを知っているからか、照れはしても彼女はこういうところで伝えることを躊躇わない。強いなぁと思う反面、そんなところが彼女の弱さなのだろうとも思う。
戦線に出るたび、細い、いつ切れてしまうとも分からない約束を交わして。離れてしまう直前にはこうして肌を重ねるのが、俺たちの決まりのようになってしまった。互いの存在を刻むかのように、忘れないように。またここへ戻ってくるという、誓いを込めて。
また近々、彼女は戦場に出るだろう。悪化の一途を辿っている戦線は、もう彼女を戦場から退かせることの出来ないところまで来てしまっている。彼女も自身の任を投げ出すような性格ではないし、他人に押し付けることになるくらいなら、笑ってどんな死地にも出ていくだろう。それが分かっているから、胸が不安で潰されてしまいそうになるくらい、不安で……苦しい。
寝台にそっと身体を下ろして、そのまま顔を埋めるようにして抱き着いた。結局こんなときにも立場と責務に縛られたままの俺も、彼女も、嘘は吐かないにしても、きっと心の底で燻っている本音を、互いに素直に吐露することは出来ていない。分かっていて、その事実から目を逸らす。
言葉にできないから、ただしがみつくように抱き着いてぬくもりを感じて。緊張で震えた吐息を隠すように、じっと息を凝らす。
「……何を不安になってるんですか、中尉。まだ私はここにいますし、次があっても帰ってきますよ」
約束を違えたこと、これまでにありましたかと薄く笑みを滲ませた声が、やわらかに降ってくる。ふわり、と。撫でられた頭に、彼女の体温が染み渡っていく。
「うん、大丈夫。不安になったわけじゃないんだよ、久遠ちゃんは今言った通り、約束を破ったことはないから。……信じてる。だけど……、ごめんね。今はこうしていて……」
不安なのだと。代わってあげたいなどという言葉は到底、言えなかった。だって俺がここにいるために、キミは茨の道を進んで歩いている。
自分の命と俺の命を秤にかけて、そのときキミは、迷わずに俺の命を選ぶんだろう。自分が死んでも俺が生き残るならいいと、そのときが来ても後悔のないように、悔いなく生きようと。そのために、不安は全部自分の中に押し留めて……それでいて、それ以外の心と身体は、俺に明け渡してくれる。
強いけど、残酷で。俺がキミを失っても、きっとこの〝中尉〟という役職に縛られている以上、後を追うことも出来ないと知っていて……。キミはその選択を、悔いなくする。
本当に、強い子を好きになっちゃったなと自嘲気味に笑った。さすが、我が軍で最も苛烈で熾烈な部隊を率い、この戦火の最前線を何度も潜り抜け、何度もこの地へ帰還をしている部隊長だ。
「いいんです、不安になっても。私だって戦場に出るときは、不安がゼロなわけじゃありません。でも、絶対に帰ってきて〝ただいま〟を言うって決めているので」
そのためだけにがむしゃらになっているだけですと、薄く彼女が笑う。その声が、じわじわと俺の裡へと降り積もっていく。
「……だから、千弘さんにはここにいてもらわないと困ります。私が帰ってきたときに、おかえりって出迎えてくれる人がいなきゃ、寂しいじゃないですか」
いつだって、キミの言葉で俺は救われている。そっかぁ、と情けないほどに震えた声でそう応じて、ようやく顔をあげた。
「……そうだったね。俺の役目はここで、キミのことをおかえりって、出迎える役だ」
ぽんぽんと軽く頭を撫でたあと、ふわりと笑う彼女の瞳が、痛みを堪えるようなそれになっていることにも、気付いていて。何も言わない彼女の強さに、結局俺は甘えていたのかもしれない。
「ところで千弘さん、私このまま放っておかれるとさすがに疲労で寝てしまいかねないんですけど。……いいんですか?」
「だーめ。しんみりしちゃって、お預け食らわせちゃったけど……ちゃあんと、キミのことを愛させて。ね……?」
そう言って軋む寝台へ乗り上げながら、彼女の躯体を引き倒す。
◇ ◆ ◇
「……え……?」
大佐に呼び出され、伝令としてひと足先に戻ってきた彼女の隊の軍曹の告げた言葉。その意味が理解できずに、俺は冷静な中尉の仮面をまともに被れなくなってしまった。
「神里准尉が、怪我……を?」
鸚鵡返しのような、言葉しか紡げない。
「……はい。戦闘自体はつつがなく終了しました。我が隊の勝利です。ですが……准尉は、掃討後の生存者確認のための見回り中――、かろうじて生存していた敵兵のひとりが仕掛けた爆弾で……」
敵兵の骸の間に埋もれるようにしていたために、生存者がいることに気付くのが遅れたこと。……その敵兵が、運悪く砲兵だったために、彼女が近付いたタイミングで無事だった砲弾ごと火をつけたこと。気付いた彼女は部下に対して鋭く、命としてこの場から下がることを告げたこと。その部隊長命令中、准尉の声を掻き消すようにして上がった轟音と敵兵たちの骸を吹き飛ばすほどの爆風に、煽られるようにして体勢を崩した准尉が、受け身も取れずに岩場に放り出されたこと。
――落下地点が悪く、頭部を殴打……負傷し、意識不明の状態であること。
それらすべてが、軍曹の口から説明された。
俺はと言えば、その報告がまったくと言っていいほど頭に入らなかった。みるみるうちに全身から血の気が引いていく。色を失い、恐怖から唇が戦慄き出す。悟られぬように唇を薄く噛み締めて、ただひと言、「そうか……」と絞り出すように応じた。
「……部隊への、損害は……」
「掃討後の哨戒は隊長が自ら行っていたため、隊への損害はありません」
迸りそうになる悲鳴を必死で喉に押し込めて、「それは不幸中の幸いだ」と思ってもいない言葉を返す。スルスルと、俺の気持ちとひとつも一致しない言葉が出てきて、平気でその言葉を紡げることに、ひどく苛立った。
「……神里准尉の容態は」
「外傷はほとんどなく、ただ打ちどころが悪かったために、意識だけが戻りません。……ここへの帰還は、早くて一両日中、には」
「わかった。……よく帰ったな、下がっていい。キミもゆっくり休みなさい」
言葉を紡げずにいると、やんわりと大佐が口を挟み、軍曹に帰るように告げる。俺はそれを止めることもできず、ただ頭を下げた軍曹が部屋から退室していくのを眺めていた。
「……っ」
押し殺していた声が、溢れる。止まらなかった。
「……高嶺中尉。気持ちはわかるし多少慮ってやることもできるが、ここを出るまでに部下に当たることのないよう……覚悟だけは、しておくように」
そう言い残して、大佐は自身の広い部屋に俺をひとり置いて部屋を出て行ってしまった。人払いは、してあるのだろう。この差し迫った状況においても、大佐のところや、俺のところには日中ほとんどの兵は尋ねて来ない。そう、これだけ戦況が激化していても、俺たちの仕事に、やることは変わらないのだ。人員が減り、削減された役もある。だが、将校以下のやることだけは変わらない。
あの子が命を賭けている間に、俺がやるのは命の危機など微塵もない、書類仕事だ。どうしてあの子が戦場にいるのに、俺はこうしてぬくぬくと安全な場所にいるのか。思いを告げたときに、覚悟していたはずなのに。彼女のことがどんどんと手放せない、手放したくない存在になっていったから、こんなときになって、馬鹿みたいに自分の本音を思い知ることになる。縋ればよかった。行かないでと。せめて伝えることを諦めずに、俺の本音はこうなんだと、そう伝えることくらいは躊躇わなくても良かったのではないか、と。
無事でいてくれと、ただただ祈ることしか出来ない時間の中、何度も手を合わせ、震える吐息を吐き出した。彼女が帰ってくるまでの時間が、こんなにも長い。あの子が笑顔で帰還を告げてくれることがないと、分かっているだけでこんなにも息ができなくなるのだと、俺は、この日はじめて自覚した。
◇ ◆ ◇
「第三部隊、ただいま帰還しました!」
司令部に、声が聞こえる。にわかに騒がしくなる外の喧騒を、どこか他人事のように聞きながら、視線を落としていた書類から顔を上げた。
読んでいたわけじゃない。昨日話を聞いてから、ろくに書類仕事が進んでいない。表向きはいつも通り。でも、ひとりで静かな執務室にいる間、気付けば彼女のことばかり考えている。
帰還を告げる声が、彼女ではなく……彼女より上位の古参の少尉の声だということに、また身体の芯が冷えていく心地を覚えながら。立ち上がって、執務室を後にした。
俺の、仕事は――……彼女たち、部隊の帰還を迎えてあげることだから。
「……神里准尉は?」
医務室に入って、医官にそう尋ねる。ああ中尉、と応じて彼は奥に設られた半個室のように目張りのされた寝台を示した。意識のない彼女に配慮したのだろう。急拵えのその様子を見ると、やはり軍などという場所は、基本的に女の子が生活することを前提にしていないのだと、まざまざと実感させられる。
目だけで応じて、足を向けた。目張りを軽く叩いて、顔を出す。中では看護官が何がしかを書きつけているところだった。目礼を受けて、俺も軍帽を軽く持ち上げて応じる。
部隊の面々は報告などもあるのか、この場にはいないようだった。ベッド脇に申し訳程度に置かれた丸椅子に腰を下ろす。本当は聞くのであれば軍医が良いのだろうが、口を閉ざしていることにも耐えられず、俺は口を開いた。
「准尉の様子は?」
震えを隠すために、押し殺した声は思った以上に険しい声音になってしまった。
書き付けから顔を上げて、看護官は眉根を寄せて難しい顔をしてみせる。
「怪我自体は大したことありませんよ。吹き飛ばされた時の衝撃でできた打ち身はひどいですが、骨折もありません。でも、打ちどころが悪かったので……場合によっては、目覚めないまま……亡くなることもあるでしょうね」
あんなに元気で、いい子だったのにと小さく小さく付け足して嘆息した彼女の言葉が、右から左へと抜けていく。そう。わかってはいたはずだった。医療も不十分なここでは、頭部殴打となっても、その中が無事かどうかなどわからない。あとは彼女の生命力に賭けるしか、方法はないのだと。
分かってはいたけれど、一縷の希望に縋って保っていた心が、瓦解していく音が聞こえる。他の何を犠牲にしてもいい。だからどうか。神でも、なんでもいい。助けてくれるのなら。もう一度、彼女と話がしたい。噛み締めすぎた唇から、鉄の味がする。いつの間にかひとり残された空間で、彼女の無事を祈って、ただ手を合わせた。
――こんなとき、俺がいても出来ることがないことが、こんなにも歯痒い。傍にいたところで、手も握ってあげられない。ただ、執務室でひとり縋るような気持ちで祈っていたときと同じように、祈ることしか出来やしない。
◇ ◆ ◇
それから俺の日課は、毎日執務の合間に医務室を訪ねることになった。
状態は落ち着いている、小康していて急変の兆しは見えない。そんな報告に、ただ胸を撫で下ろし、眠る彼女の顔を見つめるだけ。
今日も、そうだった。そのはず、だった。
「……!中尉!准尉が目覚めました……!」
「……え?」
部下のその声に、慌てて顔を向ける。話し込んでいたはずの軍医を放って、彼女のところへと駆ける。
「……っ、久遠!……よかった、戻ってきてくれて」
きょとんと。事態が飲み込めない様子の彼女に、声をかけて事情を説明する。
「ここは医務室だよ……キミは三日前にここに運び込まれて、ずっと眠っていたんだ」
安心させるように、やわらかな声で。喉が震えて涙声にならないように、細心の注意を払う。
困った顔をして、彼女の瞳が俺を捉える。剣の抜けた、険しさのない表情。あんなにも勇敢な戦士の顔をしていた面影など、そこにはなかった。ただ、本当に困った様子で、瞳を揺らす。あどけない、その……表情は。
「……?……どうしたの、そんな顔で俺を見つめて……?」
嫌な予感がした。また急速に、身体の芯が冷えていく。目が覚めたら、おかえりと声を掛けて。あの夕焼けの屋上で交わした約束の続きを告げるはずだった覚悟は、宙ぶらりんで置いていかれる。
嗚呼、そうだった。何をしてもいいから、と望んだのは俺だ。であれば、これはきっとチャンスなのだろう。何もかも……俺のことも含めて、本当に何もかも忘れてしまった准尉を、元の生活に戻してあげるには。
きっと、これが一番の好機なのだと。そう、自分に言い聞かせて、伸ばしかけていた手を、強く握りしめた。
爪が手のひらに食い込むほど、深く。痛みを戒めにするために。
――次は、俺がキミを助ける番だから。誰も知らない約束を胸の裡で反芻して、折れそうになる心を、叱咤する。そうして俺は、彼女の上官としての表情を張りつけて、俺と彼女の身分を説明するために、口を開いた。
――金切声を上げる心に、蓋をして。
目次へ戻る
読上
募る想い
2021/11/23
「おつかれっした~」
「おつかれ~」
ミーティング終了の声とともに、その声が部屋の各所で次々と上がる。
伸びをしながら出ていく人、あくびを噛み殺して出ていく人……色んな人がいる中で、俺は人が殺到する出口の方をぼんやり眺めて、佇んでいた。
疲れていない、と言えばうそになるけれど、それは疲れたというよりも飛行機に乗っている間、窮屈な思いをした……くらいのしんどさだ。
この胸の、喪失感よりも耐え難いものなんて、今の俺には見つからない。
「チヒロ、どーした?さすがのお前も疲れたか?」
「トーちゃん……。ううん、疲れは平気なんだけどね」
何を、とは言えずに曖昧に笑みを浮かべる。同じ事務所の男優の中でも特に仲のいいトーちゃん――渋木藤次郎は、すでに彼女とも顔を合わせたことがある。
そういえば、富士野飛沫丸という芸名をふざけて教えたときの、彼女の事態が飲み込めないといった疑問符いっぱいの表情は可愛かったなぁと、また彼女のことを思い出す。
何かひとつ考えるたびに、彼女とのことを思い浮かべてまた寂しさを勝手に募らせていっているなんて、自分でも馬鹿だなぁと思う。
寂しいという想いは口にできても、さすがに彼女にも、キミと過ごした日々を思い出すようなことがあるたびに、余計に寂しくなっていくなんてことは言えなかった。だって、寂しいのは彼女も同じはずだから。あの子が笑って喜んでくれているのに、俺だけが寂しいと言うのは、なんだか卑怯な気がしてしまう。
「あ~……、あれか?さっきの自由時間に、もしかして彼女さんに電話でもしてきたか?」
「……うん、まあね。さすがトーちゃん、分かっちゃうんだなぁ」
「いやお前飛行機でもずっとそわそわしてたし、俺しか知らないってのはあると思うけど……ずっとあの子のことばっか喋ってるぞ?」
さすがに付き合いも長いしそれくらいは俺でもわかるわと笑った友人の言葉に、自分自身そんなに彼女のことばかり話していたのかと、内心反省する。
最近は社長も岡持っちゃんもトーちゃんも、俺の周りの人は彼女のことを当たり前に知っていたし、お仕事に着いてきてもらう日もあって、すこし気が緩んでいたのかもしれない。
甘えていたと言うべきだろうか。俺のこの女性不信を知っている人は少ないけれど、代わりにそれを知っている人たちは皆、彼女との出会いをよかったねと応援してくれる。
そうではない仕事上のお付き合いの人も、以前よりパフォーマンスを上げられるようになった俺と、その変化を聞いて「彼女さんにお礼言っておいてくださいね」と言ってくれる人ばかりだったから。
「まー社長もお前には言い寄ってくる人間も減るだろうし、隠さず言っていいって言ってあんだろ?ならまあいいだろ。声聞いて寂しくなるとか、普通にあることなんだし気にすんな」
ほらもう遅いし、出口も空いてきたからそろそろ行こーぜと肩を叩かれて、歩き出す。
それから先、部屋に戻るまでは明日の撮影についてだとか、ここしばらくの近況だとかの、これまで通りの他愛ない話をして、トーちゃんと別れた。
部屋に戻って、誰もいないベッドに腰かける。気を遣って岡持っちゃんが手配してくれたひとり部屋は、リゾート地ということもあってか、ひとり部屋の割に間取りが広い。
なんだか、彼女が家に来る前の、無機質で最低限の物しかない、だだっ広くて冷たい我が家を思い出してしまう。
「んー、明日も撮影だし早くお風呂済ませて寝ないとね……」
彼女が来てからの俺の家は、すこしずつ物が増えて、色が増えて――それと一緒に、部屋での思い出も増えて。
冷たくて凍えてしまうようなベッドで眠るのではなく、あの子の体温と、充足感に包まれて眠るようになって、今ではそれが当たり前になった。
……だからだろうか。ひとり寝がこんなにも寂しくて、冷たいシーツが肌だけではなく胸の奥まで刺すように感じてしまうのは。彼女はいつものあの部屋で、なにを考えてどう思いながら、今日は眠りについたのだろう。
そんなことを考えているうちに、まどろみが訪れる。鈍くなった思考で、それでも彼女のことを考えたまま、意識はゆるやかに落ちていった。
◇ ◆ ◇
昼休憩の時間に、俺は珍しく箸を止める。
「どーしたんだよチヒロ。食欲ないのか?まさか、今になって時差ボケか?」
黙々と出された食事に手をつけていたトーちゃんが、そう声をかけてくれる。ううん、と緩やかに首を左右に振ってから、やや不満げな声を出してみせた。
「んーん、もうちょっとだったのにトーちゃんに負けたの悔しいなーって考えてたんだよ」
午前の撮影で開催されたビーチフラッグのことを話題に上げて、そう言ってみせる。
ああと笑ったトーちゃんは、止めていた手を再開させてからからと笑う。
「いやー、俺だってまだまだお前らには負けてらんねぇよ」
その声に、他の面々も続々と声をあげて反応してくる。
「ていうかふたりが強すぎんだけど。なにお前ら。もうちょっと縮んでからやり直してくれない?」
「持って生まれた体躯はどうしようもないだろー。はーでもあんなガチで走ったのいつぶりよ?」
「俺、今朝ふっつーに日本時間のままで朝のアラームかけてて寝坊しかけたから、ガチで走ったの今日の朝イチ♡ いやー、猛ダッシュだったわ〜」
「お前がやらかすのは納得だわ」
「いやひどくない?息切れもせずに到着したし、ちゃーんとその後も動けてたっしょ!?」
「あ、あの猛ダッシュの集合シーンも使うつもりで撮ってあるから〜!」
「……え、マジで?ちょっとそれは恥ずくない?」
同じ事務所の人間と、顔馴染みのスタッフ。だから基本的には気安い関係だし、こうして他愛もない話題で盛り上がれる。
これまでの俺なら、こういう場ではもっと楽しんでいただろうと思う。気を張らなくて済む――それだけで、ひと心地つけていたから。
休憩中にはこんな風に盛り上がって笑って、その後も和気藹々と撮影は進んでいく。思ったよりも盛り上がりすぎて、撮影が押したり。テープチェンジの休憩だったりで、あんまり自由な時間はなかったけれど。それでよかったかもな、なんて考えたりもした。
――だって、きっと自由時間に行く先々で、あの子と一緒だったら……って考えてしまう。これを見たらあの子はどんな反応をするかな。こういうのは好きかなぁ、とか。小さな仕草も、言葉も、表情も……全部、鮮明に思い浮かんでしまうくらいに。
「……やっぱり、恥ずかしいからダメって言われて取り上げられちゃったけど……久遠ちゃんの服、持ってくるんだったかなぁ……」
うーん、と湯船に浸かりながらそんな声を上げた。こんな風に弱音を吐くなんて、自分自身のことながらに珍しい。
ここで出てくる食事も美味しいけれど、どこか物足りない。味気ない。ふたりで作ったごはんを囲んで、なんでもない話をしながらあの子と食べる食事に、勝るものがない。ここへ来てから、ずっと満ち足りない。飢えを抱えた獣のような、淡い飢餓感を感じながら、吐息をこぼす。
ざぶりとお湯を手で掬って、ただそれを湯船に戻す動作を何度か繰り返す。不満があるかと問われれば、仕事に対して不満はない。……ないのに、こんなにも寂しいと感じてしまう。
いつも使ってるシャンプーやボディーソープの匂いが急に恋しくなる。彼女と同じ匂いに包まれているだけで、なんだか安心できるから。思った以上にあの子のことが大事で、愛しいんだなと自覚したら、もうそれだけで胸がいっぱいになった。
誰も俺を見てくれないかもしれないと。「高嶺千弘」そのままで受け止めて、受け入れてくれる人はいないのかもしれないと思っていたから。あの子の体温がすぐ傍で、触れられる距離にあり続けてくれることが、もうとっくに俺にとっての何よりの支えで、原動力になっている。
今日はもうすこし我慢して、彼女が眠る頃になるまで電話を待とうと思っていたけれど。考え始めたら、もう気持ちが抑えられそうになかった。
このところ、何をするにもあの子が一緒で、何をするにもいつもと比較をして寂しくなってしまう。――お風呂に入るのだってそう。小柄な彼女の身体を後ろから抱きしめるようにして浸かる湯船に慣れてしまって、ひとりで手足を伸ばして入るそれに、むしろうら寂しさを覚えてしまうくらいには。
お風呂を出たら、予定よりすこし早いかもしれないけど、あの子に電話をしよう。気ばかりが急くなかで、バスルームを後にする。濡れた髪もそのままにして、ただ早く早くと焦れる心のままに。
眠気に抗う彼女の、ふにゃふにゃと溶けていくような呂律で紡がれる声も。とろんと落ちはじめた瞼も、ぜんぶ俺を満たしてくれるから。ひとつたりとも逃したくない、なんて。キミには言えない感情を胸にそっとしまって、コール音のあとで名前を呼ぶ。
「久遠ちゃん、おまたせ」
◇ ◆ ◇
汗ばんだ肌が吸いついたその感触が、いくらか時間が経ったのにまだ心地よくて、手放せないでいる。
体温も声も、そのひとつひとつの仕草もぜんぶ逃したくなくて、無理をさせているのもわかっているのに、何度も際限なく彼女を求めた。
結果、最後にはほとんど気を失うようにして眠ってしまった彼女の身体を抱きしめたまま、胸の奥に広がるあたたかさを噛み締めて、俺はただぼんやりその寝顔を眺めている。
するりとその肌を指先で撫でて、彼女の華奢な腕に嵌ったままのバングルに視線を落とす。
見立てに自信はあったけれど、実際にその腕に嵌めたところを見ているのとはワケが違う。その肌の色によく映えて、きらきらと照明の光を受けて静かに存在を主張する様子に、じわりと、色んな感情が溶けていくのを感じる。
腕に嵌めてバングルを彼女に渡したとき、揺れる瞳でこちらを見て小さく息を吸い込んで。震える声音を隠しもせずに、腕を抱くようにしてそれに唇を寄せた彼女のいじらしさに、胸が押しつぶされるほどの幸福に包まれた。
何度も嬉しいと気持ちを伝えて、泣き出しそうな顔で笑う久遠ちゃんを見ていたら、押し留めていた感情が、簡単に決壊していく。
掻き抱きたくなるほどの愛しさをそのままに、手を伸ばして、想いも熱も、ぜんぶをぶつけて。
――通話なんかじゃなくて、その可愛い声を直接聞かせて。画面越しなんかじゃなくて、その唇にキスをさせて。直接触れてキミの熱を感じさせて、キミも俺の熱でいっぱいになって欲しい。……なんて、尽きることのない欲求を、何度も何度も言葉と、行為と、溢れて止まらない熱で、注ぎ込んだ。
ふわふわと纏わりつくような眠気が、じわじわと身体を侵食していく。回らなくなっていく思考で、最後にその額に軽く口づけを落とす。
溶け切った体温に思考まで溶かしてしまうように、何もかもを放り投げ、明日無理をさせたことを謝ろうと考えつつ、ただかけがえのない人の傍で、眠りについた。
目次へ戻る
読上
渇愛と獣慾
2021/11/14
「ふふ、本当に気に入ったんだね?」
ふりふりと左右に尻尾を揺するたび、彼女の視線が注がれる。尻尾の動きに合わせて視線が左右を往復する様子を見て、なんだか猫じゃらしを前にした猫みたいだなと思った。
そう考えたら、キミに耳や尻尾が生えなかったことがすこし残念になる。ふわふわの髪の合間からぴょこんと覗く耳なんて、それは可愛かったろうになと考えながら、そう声にしていた。
「……えっ、あ……すみません。つい、また目で追ってしまってましたね……?」
恥ずかしそうに俯いて、久遠ちゃんがはにかんで笑う。もふもふした動物に目がないんですと笑っていた彼女は、その通りずっと俺の尻尾の動きを目で追っている。久遠ちゃんが気に入ったならもうしばらくはこのままにしようか、と提案したのは俺だけれど。あまりに素直にその提案を受け止め、ふわふわの触り心地を楽しんでいる彼女の様子を見ていると、本当にしばらくはこのままでいいかもしれないと思った。
「いいよ、見てても♡ 久遠ちゃんが俺のことをずっと目で追ってくれるの、悪い気はしないしね」
そう言って、ほんの少しイタズラに笑う。
普段の俺は、仕事の休みも不定期で朝から晩まで撮影の日もあれば昼過ぎからのスケジュールだったりと、何もかも一定であることはない生活をしているから。たまにこうしてまとまった休みがある贅沢を、楽しんでもきっとバチは当たらないだろうしね。
「じゃああの……千弘さん。また、尻尾もふもふしても……いいですか?」
「もちろん。はい、どーぞ♡」
おいでと手招きをしてみせると、彼女はうれしさを隠せない表情でぱたぱたと駆けてきて、俺の隣に腰を下ろす。その素直さも、〝俺だから〟こうして来てくれていることもわかるのに、どうしてかうれしいけれど複雑で。いつもよりほんのすこし、意地悪な気持ちが湧き上がってしまう。
……彼女は普段、毎日俺が触れることを許してくれるし、もっともっとと求めても、それに応じてくれる。けれど存外、彼女の方から俺にこうして求めてくることは少ない。
だから際限なく求めてしまいたくなるけれど、どう考えても体力的にも優位性があるのは俺の方で。こういうとき、自制をしなければならないのはわかってるから、困らせたい気持ちと、ちゃんと約束を守らなきゃという気持ちと、ふわふわして柔らかくて甘い、俺にとっての最上のご馳走に溺れてしまいたい気持ちと、全部が胸中で綯い交ぜになって、身動きが取れなくなっていく。
彼女が俺を気遣ってくれる気持ちも知っている。何度彼女に「仕事でも一度もスタミナ切れを起こしたことはないんだよ」と話をしても、求めれば欠かさずに千弘さんは大丈夫ですかと聞いてくれるし、そんなところが好きだなと思う。
聞いて、俺がこの時間を楽しみにお仕事を頑張ってきたんだよと言えば、顔を赤くしながらも俺の求めに応えてくれるところが、本当に。――心の底から|慕《した》わしい。
「それにしても、何度撫でられても尻尾の感覚があるって不思議だなぁ……」
やさしく、梳くように手を動かす彼女の指の動きを眺めながら、ぽそりとそんなことをつぶやいた。
「不思議ですよね……本当に。尻尾があるってどんな感覚なんですか?」
「うーん、言葉にするのは難しいけど……腕とか足がひとつ増えたような感覚だと思ってくれて間違ってないよ」
「な、なるほど……!あれ、と言うことは私は今、千弘さんの腕を執拗なまでに愛でる人になってますか?!」
「ふふ、まあここに実際あるのは腕じゃなくてもふもふでふわっふわの尻尾だからね……♡ なにより、俺が気にしなくていーよって言ったでしょ?」
興味津々と言った風で、質問を投げかけてきた彼女を諭すように、ぺたんと器用にその腕を撫でるように尻尾を動かす。尻尾は凡そ感情のままに動くみたいだけど、慣れればある程度は自分の意思で動かせるようになったので、外出しづらい以外に困っていることはなかった。
「あ、でもそうだな。代わりに、久遠ちゃんが満足したら……俺にもキミをぎゅってさせてくれる?」
ずっとキミに見られて、撫でられてたら俺の方も満たして欲しくなっちゃった♡と囁くように耳元で告げる。
赤くなってその指を止めた彼女に、だめかなと笑いかけた。赤く染まった頬を、指先でなぞり視線を合わせると恥ずかしそうにその目が揺れて、戸惑うように俺を見上げて。
「……は、い……」
……ややあって、照れを滲ませた声がした。きゅ、とわずかに指先に込められた力が尻尾から伝わる。それだけでもう、愛しさが溢れて止まらなかった。
◇ ◆ ◇
すり、と鼻先を肌に埋めてその体温を感じる。
耳と尻尾が出てから、いつもより鋭敏になった鼻に彼女の匂いがふわりと届いた。
俺と同じシャンプーを使っているはずなのに、彼女の匂いと混ざるともっとずっと甘くてやさしいものになる。
「ふふ、本当にいい匂い……♡」
すりすりと何度も首筋に鼻を摺り寄せて、胸いっぱいに匂いを吸い込む。
くすぐったいのか逃げるように顔を逸らそうとするのを追いすがり、ふたりでベッドに倒れ込んだ。覆い被さる形で倒れ込んで、真正面から瞳を合わせる。
「……あの、千弘さん……?ぎゅってするだけじゃ……なかったですっけ……」
「うーん、そのつもりだったんだけどね。今日はずっとキミに見られてたわけだし、抱きしめたら止まらなくなっちゃった……♡」
いつもならその柔らかな内腿に指を這わせて触れるところを、今日は尻尾を絡めて毛先で肌を撫であげて。
毎夜のようにこの場所でこうして愛されている彼女が、ちゃあんとそれを連想するように、じわじわと燻る熱を共有していく。
「ね、今日から三日間はおやすみもらえたわけだし……いつもはちょっとだけセーブしてるけど、今日はいっぱい愛しても……いいよね?」
そう言って首筋に唇で触れる。やさしく食むようにして、何度も唇を寄せるたび、キミの内側で焚きつけられていく火が大きくなっていく。
触れるたび小さく震える喉を見て、反射的に唇を舐めた。やさしくしているけれど、俺はいつもキミを求めて、狩る側の立場にいる。
困ったように眉根を寄せて、口を開いて――それでも、何も言えずに一度口を閉ざしてから。潤んだ瞳で俺を見上げて、震える声と熱を持った吐息がキミの喉から零れ落ちる。
「……っ、はい……」
その返事を合図にして、噛みつきたい衝動を殺しながら答えを紡いだ唇にキスを降らせた。
早く、俺だけでいっぱいになって。ただただ、愛らしい声で啼いて、俺の名前を呼ぶ姿を見せてほしい。キミが、どうしようもなく俺でいっぱいになってくれることが、一番充足感を与えてくれるから。
目次へ戻る
2021年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
読上
滲む幸福
2021/10/30
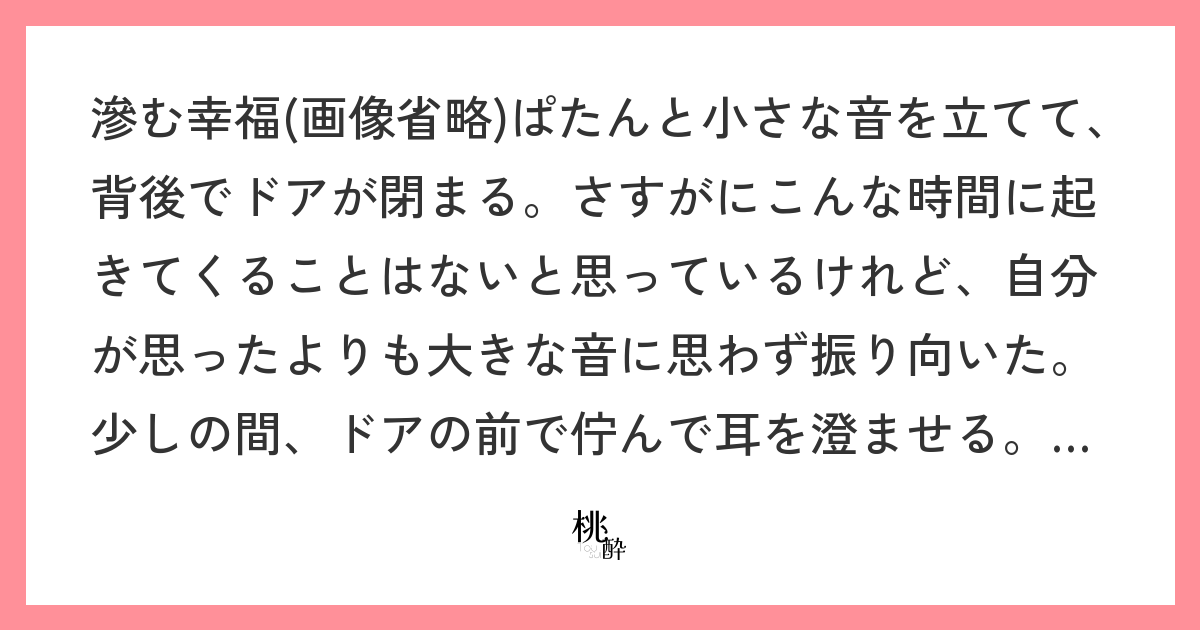
ぱたんと小さな音を立てて、背後でドアが閉まる。
さすがにこんな時間に起きてくることはないと思っているけれど、自分が思ったよりも大きな音に思わず振り向いた。
少しの間、ドアの前で佇んで耳を澄ませる。
大丈夫。布擦れの音はしない。あの子はきっとまだ寝ているだろう。
隣ですやすやと寝息を立て気を許しきった、警戒心など皆無な様子で眠りこける彼女の表情を思い浮かべると、ひとりでに頬がゆるむ。
喉を潤そうと部屋を出たはいいものの、いざ部屋を出てしまうとなぜかその気持ちが少し薄らいでしまった。
すこしだけ躊躇してから、リビングに置かれたソファに腰を下ろす。
水も飲まないのならすぐに戻ればいいだろうに、今はどうしてかその気持ちになれなかった。すこし、冷静になりたい。彼女といると、冷静さが欠けてしまう。
紳士的でありたいと思うのに、同時に苛烈に求めたくもなる。相反した思いが、身体の中でない交ぜになっていく。どちらも自分の本心なのが、余計に厄介だ。
天井を仰いで、ゆるく目を閉じる。これまで満たされたことのないくらいの気持ちに、自分自身が負けそうになるなんて。そんな風になることがあるということに、自分自身でもすこし驚いた。
「ほんとに、予想外のことばっかりだなぁ……」
事故的に触れた、初めて出逢った日のことも。うまく隠してきた弱みを知られてしまった日のことも。
それこそ完全な事故だった――完全に気を緩めている状態で、触れた瞬間のことも。
言ってしまえば何もかもが予想外で、ぜんぶが規格外で。不思議な出逢いをしたものだなぁと、じわじわと実感する。
「……って、ちょっと感慨に耽りすぎたかな」
ふと壁の時計に目をやり、慌てて腰を上げた。
すこしぼんやりしていただけのつもりだったのだが、思った以上に時間が経過している。職業柄、時間感覚もまあまあある方なのになと自嘲気味に笑いを溢す。
本当に、ここしばらくは、いつもそうだ。彼女のこととなると、どこか自分が自分でなくなってしまう。
いい加減当初の目的を果たしてから眠りにつこうと、キッチンへ立ち寄る。常時何種類か冷やしてある作り置きのそれらをスルーして、無機質なミネラルウォーターのペットボトルを手に取った。冷蔵庫から漂うひんやりとした冷気に、のぼせた思考が急速に落ち着いていくような気がする。
……これでいい、と思う。
これでいいと思うのに、これではないと思う気持ちもあって、ああ、俺は本当に彼女に恋をしているんだな、と柄にもなく感じた。
あんまりゆっくりしてると起きちゃうかもしれないし、とじわりと温かくなっていく心から目を背けて、無心でペットボトルの蓋を捻る。
冷えた水の温度が、のぼせそうな気持ちを引き戻してくれる気がして、なぜだか無性にほっとしたのだ。
こんなことを考えているなんて、彼女に知れたら一体どうなるだろう。
……それが、怖い。彼女が見ているのは幻想でも何でもなく、きちんと"高嶺千弘"という人間を見てくれたから、俺はあの子を好きになったのに。
そんなことを言った俺の方が、変質してしまいそうになるなんて、考えていなかったから。
こくり、と嚥下した音が静かに無機質なキッチンに響いた。
殺風景な部屋。生きていくのには困らないけれど、なににも彩られていない――、俺の部屋は、そんな空間だ。
冷蔵庫に水を片付けて、視線をふとあげる。目に入ってくるのは、夕飯後に片付けた不揃いの食器だった。
彼女はここで俺と一緒に暮らしているけれど、まだ客用のものや予備の食器を使っている。そのせいで、食事を終えたキッチンにはこうして無骨な食器が並ぶことが多い。
ふと、欲が顔を出す。
彩ってみても、いいだろうか――と。
きっと、あの子は拒絶しない。笑って「いいですね」と受け入れてくれるのだろう。
けれど俺は、絶対拒絶されないという自信と裏腹に、気付かれない程度に……ほんのすこしだけ、その問いを息を詰めて尋ねるのだ。
水の中にいるような、やわらかな息苦しさ。そこから解放してくれるのは、いつも彼女の答えだけなのだから。
そのことに気付かない君の、やわらかで純粋で……真っすぐな瞳に、焦がれている。
「ふふ、そろそろ戻らなくちゃね」
最後に。本当に一言だけ小さく呟いて、俺は寝室へと戻った。
ここで共に住む彼女と俺の、共有する寝床へと。
◇◆◇
「……千弘さん、どうしたんですか?」
至近距離で、彼女が不思議そうに目を瞬いている。
いつの間にか、物思いに耽ってしまっていたらしい。手を止めていた俺の方に、次の食器を催促するように手を出した彼女は、小首を傾げていた。
「ごめんね、ちょっとぼうっとしてた」
「大丈夫ですか?お仕事で疲れてます?」
手渡された皿に目を落とし、水滴を丁寧に拭き上げていく様子を眺めながら、自然とゆるむ頬を必死で叱咤して俺は「ううん」と首を横に振る。
自慢ではないが、本当に複数本撮りであっても仕事でスタミナ切れを起こしたことはない。
「ちょっとね。やっぱり食器、新しくしてよかったなぁ……って、考えてただけだよ」
そう言って微笑むと、彼女は一瞬ぽかんとした表情を浮かべた後で「疲れてないならよかったです……!」とそそくさと食器を片付けに棚の方へと駆けていってしまう。
さらさらと彼女の動きに合わせて揺れる、髪の房の間から覗くその耳朶が薄紅に染まっているのを見て、俺はこっそりと笑みを深めた。
目次へ戻る