滲む幸福
2021/10/30
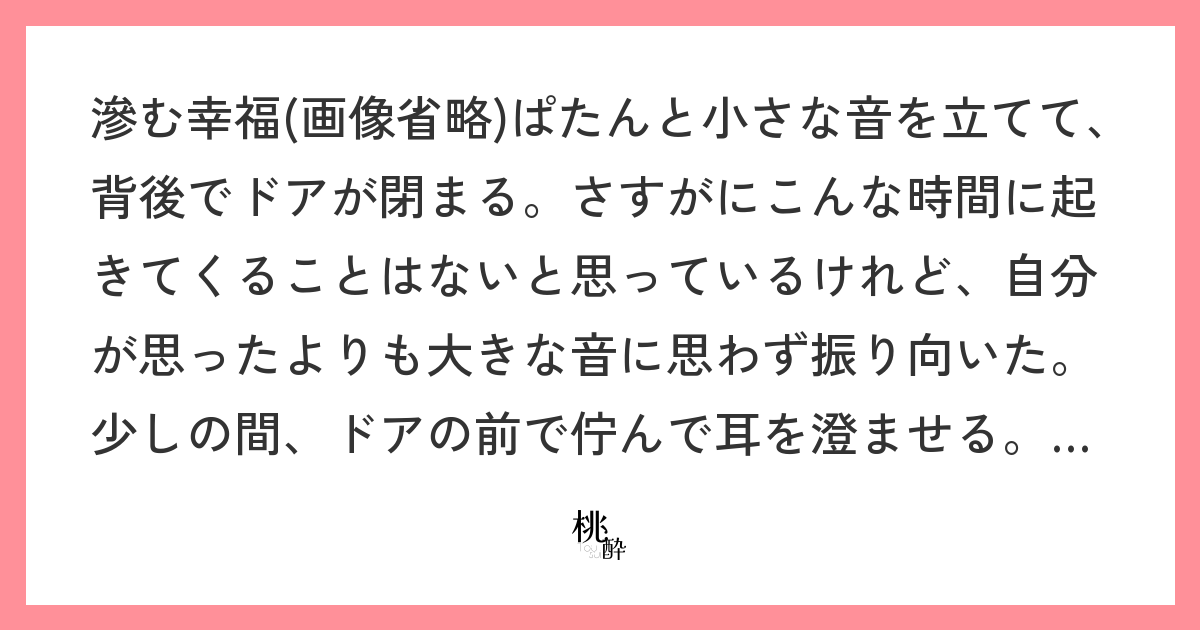
ぱたんと小さな音を立てて、背後でドアが閉まる。
さすがにこんな時間に起きてくることはないと思っているけれど、自分が思ったよりも大きな音に思わず振り向いた。
少しの間、ドアの前で佇んで耳を澄ませる。
大丈夫。布擦れの音はしない。あの子はきっとまだ寝ているだろう。
隣ですやすやと寝息を立て気を許しきった、警戒心など皆無な様子で眠りこける彼女の表情を思い浮かべると、ひとりでに頬がゆるむ。
喉を潤そうと部屋を出たはいいものの、いざ部屋を出てしまうとなぜかその気持ちが少し薄らいでしまった。
すこしだけ躊躇してから、リビングに置かれたソファに腰を下ろす。
水も飲まないのならすぐに戻ればいいだろうに、今はどうしてかその気持ちになれなかった。すこし、冷静になりたい。彼女といると、冷静さが欠けてしまう。
紳士的でありたいと思うのに、同時に苛烈に求めたくもなる。相反した思いが、身体の中でない交ぜになっていく。どちらも自分の本心なのが、余計に厄介だ。
天井を仰いで、ゆるく目を閉じる。これまで満たされたことのないくらいの気持ちに、自分自身が負けそうになるなんて。そんな風になることがあるということに、自分自身でもすこし驚いた。
「ほんとに、予想外のことばっかりだなぁ……」
事故的に触れた、初めて出逢った日のことも。うまく隠してきた弱みを知られてしまった日のことも。
それこそ完全な事故だった――完全に気を緩めている状態で、触れた瞬間のことも。
言ってしまえば何もかもが予想外で、ぜんぶが規格外で。不思議な出逢いをしたものだなぁと、じわじわと実感する。
「……って、ちょっと感慨に耽りすぎたかな」
ふと壁の時計に目をやり、慌てて腰を上げた。
すこしぼんやりしていただけのつもりだったのだが、思った以上に時間が経過している。職業柄、時間感覚もまあまあある方なのになと自嘲気味に笑いを溢す。
本当に、ここしばらくは、いつもそうだ。彼女のこととなると、どこか自分が自分でなくなってしまう。
いい加減当初の目的を果たしてから眠りにつこうと、キッチンへ立ち寄る。常時何種類か冷やしてある作り置きのそれらをスルーして、無機質なミネラルウォーターのペットボトルを手に取った。冷蔵庫から漂うひんやりとした冷気に、のぼせた思考が急速に落ち着いていくような気がする。
……これでいい、と思う。
これでいいと思うのに、これではないと思う気持ちもあって、ああ、俺は本当に彼女に恋をしているんだな、と柄にもなく感じた。
あんまりゆっくりしてると起きちゃうかもしれないし、とじわりと温かくなっていく心から目を背けて、無心でペットボトルの蓋を捻る。
冷えた水の温度が、のぼせそうな気持ちを引き戻してくれる気がして、なぜだか無性にほっとしたのだ。
こんなことを考えているなんて、彼女に知れたら一体どうなるだろう。
……それが、怖い。彼女が見ているのは幻想でも何でもなく、きちんと"高嶺千弘"という人間を見てくれたから、俺はあの子を好きになったのに。
そんなことを言った俺の方が、変質してしまいそうになるなんて、考えていなかったから。
こくり、と嚥下した音が静かに無機質なキッチンに響いた。
殺風景な部屋。生きていくのには困らないけれど、なににも彩られていない――、俺の部屋は、そんな空間だ。
冷蔵庫に水を片付けて、視線をふとあげる。目に入ってくるのは、夕飯後に片付けた不揃いの食器だった。
彼女はここで俺と一緒に暮らしているけれど、まだ客用のものや予備の食器を使っている。そのせいで、食事を終えたキッチンにはこうして無骨な食器が並ぶことが多い。
ふと、欲が顔を出す。
彩ってみても、いいだろうか――と。
きっと、あの子は拒絶しない。笑って「いいですね」と受け入れてくれるのだろう。
けれど俺は、絶対拒絶されないという自信と裏腹に、気付かれない程度に……ほんのすこしだけ、その問いを息を詰めて尋ねるのだ。
水の中にいるような、やわらかな息苦しさ。そこから解放してくれるのは、いつも彼女の答えだけなのだから。
そのことに気付かない君の、やわらかで純粋で……真っすぐな瞳に、焦がれている。
「ふふ、そろそろ戻らなくちゃね」
最後に。本当に一言だけ小さく呟いて、俺は寝室へと戻った。
ここで共に住む彼女と俺の、共有する寝床へと。
◇◆◇
「……千弘さん、どうしたんですか?」
至近距離で、彼女が不思議そうに目を瞬いている。
いつの間にか、物思いに耽ってしまっていたらしい。手を止めていた俺の方に、次の食器を催促するように手を出した彼女は、小首を傾げていた。
「ごめんね、ちょっとぼうっとしてた」
「大丈夫ですか?お仕事で疲れてます?」
手渡された皿に目を落とし、水滴を丁寧に拭き上げていく様子を眺めながら、自然とゆるむ頬を必死で叱咤して俺は「ううん」と首を横に振る。
自慢ではないが、本当に複数本撮りであっても仕事でスタミナ切れを起こしたことはない。
「ちょっとね。やっぱり食器、新しくしてよかったなぁ……って、考えてただけだよ」
そう言って微笑むと、彼女は一瞬ぽかんとした表情を浮かべた後で「疲れてないならよかったです……!」とそそくさと食器を片付けに棚の方へと駆けていってしまう。
さらさらと彼女の動きに合わせて揺れる、髪の房の間から覗くその耳朶が薄紅に染まっているのを見て、俺はこっそりと笑みを深めた。